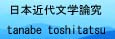|
ものぐさ 徒然なるままに日々の断想を綴る『徒然草』な らぬ「ものぐさ」です。 らぬ「ものぐさ」です。
内容は、文学・言葉・読書・ジャズ・金沢・教育・カメラ写真・弓道など。一週間に2回程度の更新ペースですが、休日に書いたものを日を散らしてアップしているので、オン・タイムではありません。以前の日記に行くには、左上の<前月>の文字をクリックして下さい。
・XP終了に伴い、この日誌の更新ができなくなりました。この日誌の部分は、別のブログに移動します。アドレスは下記です。
エキサイトブログ 「金沢日和下駄〜ものぐさ〜」
http://hiyorigeta.exblog.jp/
|
勤務先近くの書店の新刊書コーナーで見つけて、この連休に読んだ。発行(8月30日)から一ヶ月とたっていないほやほや本を買ったのは久しぶりのことである。今年になって初めてかもしれない。
私は彼を尊敬している。翻訳家として著名な人で、米国の政治家・実業家の回顧録などを手がけているが、彼の手にかかるとすべて一級の読み物になる。
私は「ライシャワー自伝」(文藝春秋社)や、ドナルド・キーン「日本文学史」(中央公論社)などで堪能した。原著自体、日米の架け橋的な仕事であり、日本語・日本文学の素養と英語の素養、その両者を兼ね備えていないと正確で魅力的な訳業は出来ない。
彼の文章の魅力を一言で言うと、格調の高い日本語だということ。表現が的確で、元の文章が外国語であることを忘れるくらいに美しい日本語に消化されている。今の時代、英語の翻訳が出来る人は格段に多くなっているが、彼ほど日本語に精通したプロを私は知らない。
この本は、自分を看取ってくれるはずと信じていた妻に先立たれるまでを描いた「喪妻記」を前半に、夫人との思い出を綴ったエッセイが後半に置かれている
文中にも触れられているが、江藤淳の「妻と私」と重なる部分が多い。妻に癌が発見され、告知をし、自宅で死を看取る。始動を始めたばかりの介護保険制度を利用した在宅看護であったこと、自身が障害者で「要支援」認定を受けての介護であったこと、子息や孫がいることが江藤との違いである。しかし、長年連れ添った恋女房を失う感情に何の違いがあるというのだろう。「文藝春秋」に発表されたこの「喪妻記」一編は、抑制された情感に溢れていて、集中の白眉である。
後半は、妻と歩んだ家族の生活記となる。彼が定年まで新聞記者を勤め上げた生粋の新聞人であることを今回初めて知った。そういえば、自分自身のことを語った文章を読んだことはなかった。
大学卒業前に見習いで赴任した支局で、デスクの目の前に座っていた彼女を見そめたこと、ベトナム戦争末期の決死の取材、住宅に窮した団地時代と、抽選に当選して一戸建てを建てるまでの苦労、マイカーを持って家族ドライブができた歓び。
十五歳で終戦を迎えたこの世代の人生は、ちょうど、戦後日本が無から出発した戦後史と重なる。慎ましやかに真面目に人生を生きてきた人である。
文章は相変わらず手堅い。例えば、「鴛鴦(えんおう)の眠りが破られた」とある。鴛は雄、鴦は雌のオシドリ。つまり、夫婦仲良く寝ていたら事件だと急に起こされたというのである。私の詞藻にはなかった優雅な言葉。よく練られて読みやすい文章の要所要所に、こういう表現がぴたっと嵌っているから効いている。
稀代の文章家が、今や老齢となり、妻を失い、片眼全盲・片眼弱視の障害者となって、不自由な生活を余儀なくされている。この文章も、大半は公にする気持ちはなく、児孫が読めばそれでよしとの思いで書き出したとある(「あとがき」)。確かに、何の変哲もない二人だけの温泉滞在の様子を事細かに描写している一編などを読むと、残された孫たちのために、爺ちゃん婆ちゃんが過ごした楽しかったあの時を書きとどめておこうという意図をはっきり感ずる。
「人生は邯鄲一炊の夢」「薤露のよう」と無常をかこつ作者の口吻から、これが最後の創作と思っているようにも思えるが、日頃、文章自体に味のある名文家がいなくなりつつあるのを嘆いている私は、彼の続く限りの健筆を祈るばかりであった。
|
 |
お願い
この日記には教育についてのコメントが出てきます。時に辛口のことも多いのですが、これは、あくまでも個人的な感想であり、よりよい教育への提言でもあります。守秘義務や中傷にならないよう配慮しているつもりです。 もし、問題になりそうな部分がありましたら、メールにてお知らせください。
感想をお寄せください。この「ものぐさ」のフォームは、コメントやトラックバックがあるブログ形式を採っておりません。ご面倒でも、左の運営者紹介BOXにあるアドレスを利用下さい。
 (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8) (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)
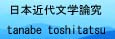
|

 らぬ「ものぐさ」です。
らぬ「ものぐさ」です。 (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)
(マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)