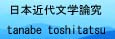|
ものぐさ 徒然なるままに日々の断想を綴る『徒然草』な らぬ「ものぐさ」です。 らぬ「ものぐさ」です。
内容は、文学・言葉・読書・ジャズ・金沢・教育・カメラ写真・弓道など。一週間に2回程度の更新ペースですが、休日に書いたものを日を散らしてアップしているので、オン・タイムではありません。以前の日記に行くには、左上の<前月>の文字をクリックして下さい。
・XP終了に伴い、この日誌の更新ができなくなりました。この日誌の部分は、別のブログに移動します。アドレスは下記です。
エキサイトブログ 「金沢日和下駄〜ものぐさ〜」
http://hiyorigeta.exblog.jp/
|
このところ、ものが壊れて、修理に出したり取りに行ったり、東奔西走。累々たる修理品の数々をご紹介したい。
学校の弓道場が新築された八年前、時計がなく、不便していたところ、卒業記念品として、部員たちが振り子時計を寄付してくれた。それ以来、三十分おきにボンボンと昔ながらの鐘を鳴らしてくれていた。生徒は背中を向けて弓を引いているので、いちいち振り返らないでも時間が分かり、重宝していた。
その時計が、先日、落ちた。プラスチックのフックの先が折れ、三メートルの高さから落下したのである。接着面が剥がれたのではなく、経年劣化で爪が折れのだが、ちょっと劣化が早すぎはしないか。
ガラスが割れ、駆動部も傷んだ。見積りは一万円。最新式を買ったほうが安いのだけれど、「卒業生一同」というのプレートがついている。悩んだ末、修理に出した。新たに鉄の柱につけなおしたフックは、一度重しをつけて耐荷重テストをするように指示した。
ほぼ同時期、自宅のミニコンポのスピーカーから音が出なくなった。端子を強く押さえると音は鳴るので、内部の接触不良が考えられる。電気店に持ち込むと、修理サービスに出す基本料(手数料)だけで六千円という。結局、ハンダが一カ所外れていただけのことで、九千円弱とられた。
銀塩カメラ(ペンタックスMZ3)のストロボポップアップのバネも壊れている。前回直してすぐにまた外れた。ネットでは、みんなこの機種の構造的欠陥だと言っている。バネのはめ直しだけで一万円強かかる。もうデジタルの時代、これはどうしたものかと、現在、思案中。
そして、なんといっても最大の修理は、去年の愚妻の誕生日プレ ゼント品。一生ものということで、大枚はたいて買ったR社のブランド腕時計である。買ってたった二か月で、落下させ、ガラスが割れてムーブメントも動かなくなった。かなりの重傷で、一ヶ月以上入院加療の上、先日戻ってきた。もしかしたら香港あたりへ海外旅行していたのかもしれない。修理代は国産高級時計が買えてしまうくらいであった。 ゼント品。一生ものということで、大枚はたいて買ったR社のブランド腕時計である。買ってたった二か月で、落下させ、ガラスが割れてムーブメントも動かなくなった。かなりの重傷で、一ヶ月以上入院加療の上、先日戻ってきた。もしかしたら香港あたりへ海外旅行していたのかもしれない。修理代は国産高級時計が買えてしまうくらいであった。
「やっぱり、分不相応なもの買うからこんなことになるんや。」ときっぱり言ったら、絶対、そう言われると思ったと愚妻。
「あの時計も、もっと大事にしてくれる御主人様のところに行きかったと思っているだろうねえ。」とさらの突っ込んでも、そうも言うだろうと思ってたという。こっちの嫌みなどとっくに織り込み済みといった風情で受け流してくる。
彼女、落とした当初はちょっと動揺していたが、今、クレジットの保険が出ないか画策中で、何か、それで免罪符になるかのような心情のようである。まあ、いいけど……。
それより、誰か、私の壊れた腰を修理してくれないものか。

(我が家の雛人形)
|
 |
|
昨年の今日、入院した。新米の若者ノリの看護士さんから入院心得を習った。あれから、ちょうど一年たつ。
一か月の入院が終わって、四月一日から正式に職場に復帰したが、すでに新年度。人員や配置が変わって、仕切り直しに忙しく、いない間、職場がどんな様子だったかは、ほとんど知らなかった。そんなこと、ゆったり聞いている暇はない。
ところが、今年に入って、学年末の諸行事の要項が出るようになり、昨年度はどうだったかという話が交わされるようになった。でも、私は、「不在だったのでわからない。」と答えるしかなかった。
あの時、季節が春へ変わったのを実感した以外は、同じ職場に戻っただけで、そんなに大きな違和感は感じなかったが、こうして、一年たった今頃になって、いなかったということを突きつけられる。
そんなものといえば、そんなものだが、これまでに経験したことのない空白に対する所在なさ感というか、何かちょっと変な感じなのであった。
|
 |
読む。といっても、もうかなりの部分、ブログ「がんばれ、生協の白石さん!」(管理人上條景介)他の紹介サイトで読んで知っている。話題の本なので、生徒がひっきりなしに借りているその合間、棚に戻っているのを見つけ、さっと借りて一晩で目を通した。本になってどう印象が違うかのほうに私としては興味があった。
周知のように、生協に寄せられた意見カードの回答が面白いということで、学生さんがネットで紹介して広まったもの。ずっと前から白石さんが東京農工大で働いているのか思っていたが、この本によると、早稲田大生協からの異動で働きだしたのは二〇〇五年になってからのことらしい。回答業務を担当し始め、それが話題になり、本になるまで一年とかかっていない(本は十一月の刊)。
出る前から、作者名をどうするか、ネット上で話題になっていた。本人の意志と関係なく、自分の仕事の上で書いた文章がネットに載ってしまっていたわけだし、質問したのは不特定な学生さんなので、色々なやり方が考えられる。結局、白石さんの本名を明記し、「学生さん」という漠然とした言い方をして両名併記という形になった。
今回の場合、『電車男』よりは特定できるが、今後も、こうしたネットネタの出版の場合、著作権をどうするかなど、問題は多そうである。例えば、今回の場合、下世話な話ながら、「学生のみなさん」の方の著作権料はどこに支払われるのだろう?
奥付に、「編集担当」として、講談社デジタルコンテンツ出版部「MouRa」、「編集協力」としてブログの作成者、「協力」として、東京農工大、農工大生協の名が見える。著者と編集者のやりとりというインティメイトな関係で成立していたこれまでの世界とは違う係わりの多さである。講談社は、ネットネタの出版が商売になると踏んで、発足して間もないネット配信を担当する新興部門を、即、これに絡めたようである。おそらく、ややこしくなるデジタル・パブリッシメント関係のノウハウは、今後、この部門が蓄積していくことになるのだろう。
もちろん、この本の本筋は、直接商品に関係のない悩み相談やおふざけ依頼にも、誠実かつウイットに富んで答えているところだが、途中、本人の解説がところどころに入っているところが重要。話題になって驚いた様子や、商売に関係のない質問への折り合いの付け方などの裏話が聞ける。そこがブログとの大きな違いである。
生協の上司やネットで広めた学生の文章も載っていて、白石さんの解説を含め、全体として、生協活動のPR、大根踊りで有名な私学の東京農大と混同される知名度の低さを払拭すべく、農工大の宣伝も入っていて、その大きな額縁の中で、掲示板のやりとりを載せているというパッケージングに仕立ててある。この本には、こうした健全な広報色があるので、大学側が今回のことを喜んで白石さんを表彰したというのも頷ける。こうしたまとめ方は、デジタルコンテンツ出版部が、出版に際してコンセプトをどうするか綿密に会議でもして決めたのだろうなと思わせるところである。
その額縁の部分が、多くの人が既に読み知っていても本を手にとらせる付加価値の部分になる。去年から急に興隆してきたネットネタ出版の初期の形としてはよく考えられたパッケージングだと思うが、ネットネタが、ずっとこういう経過報告付きの形で世に出されるというわけにもいくまい。今後、どう展開していくのだろうか。出版業界人的な興味ひとしおである。
さて、話は最後にぐっと卑近になる。
そろそろ年度末。年に一回発行の図書館報の編集が図書委員の生徒さんの手で進んでいる。原稿段階でざっと目を通したところ、この本を真似て、「○△高校の○○さん」という特集を組んでいた。図書室への希望カードに書かれた意見投書に答える形式にして、白石さん風の言い回しで、「そんな貴方にはこの本がいいでしょう。」と図書室所蔵の本を紹介している。
巧いなあ。こんなのは公務員のオジサンは逆立ちしても出てこない。
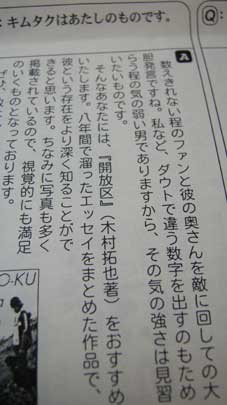
|
 |
|
十九日、詩人の茨木のり子が亡くなった。大正十五年六月生まれ、この年の十二月に昭和と元号がかわるわけだから、まさに昭和の歴史と共に歩んだ人生である。詩誌「櫂」のメンバーのうち、川崎洋は既に故人、谷川俊太郎、吉野弘、大岡信は存命である。
いい読者ではないのだが、この商売をしていると、よく教科書に出てきて、自然と目に触れることが多い人だった。
以前もこの日記で触れたことがある、彼女の『詩のこころを読む』(岩波ジュニア新書)は、自ら琴線に触れた詩をピックアップして、それを分類しコメントをつける形の入門書だが、この詩人の現代詩への感じ方が裸形で提出されており、彼女のこころの在りかがよくわかった好著。ジュニア向けとなっているが、とんでもない、全年齢向けである。
特に、この本の前半に出てくる僚友吉野弘の詩「Iwas born」への短い解説は、簡にして明、この詩の本質をすっきり教えてくれて、さすがだと思った。
「生まれる」という言葉は受身形なんだねと子供が父に話すと、父は急に蜻蛉のお腹の中にはびっしり次の生命が詰まっているのだよという話を始めたという有名な詩。
茨木は、この詩を「受身形で与えられた生を、今度は、はっきり自分の生として引き受け、主体的に把握しなければならない」という、ある意味、辻褄の合わないことを人間はしているのだということを分からせてくれる詩だと解説するのである。幾千言費やしても、この言葉にまさる解説はない。一遍で納得してしまった。
教科書に一時期、この十行ほどの解説を加えて「生まれて」というタイトルで単元化されていたことがあり、以後、彼のこの詩を授業で取り上げるときは、彼女の解説付きですることにしている。
死亡記事にも「戦後現代詩の長女」という新川和江の有名な批評が引用されていたが、彼女の初期の代表作からは、確かに、手のひらを返したような戦後の時勢に対する違和感と、のびのびとした民主主義の息吹が感じられる。戦前の痛めつけられた鬱屈した心情は、彼女にとって青春の背景にすぎず、民主主義とともに自我を開花したのびやかさが眩しいほどだ。「私が一番きれいだったとき」「根府川の海」「学校あの不思議な場所」など、彼女の代表作を読むと、あの頃青春をすごした一人の聡明な女性の姿が彷彿とされてくる。
女流詩人は数多いが、彼女の詩、他の主婦的感覚の詩人たちより、なんだか、きっぱりとして男らしい。これも代表作「自分の感受性くらい」などでは、我々大人全員、彼女から「自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ」と怒られているくらいである。
教科書には、異様にお若い頃の写真しか掲載されていないし、一度も映像などでお目にかかったこともないので、どんな感じの人だったのか、よく分からないが、写真の眼鏡をかけた知的なご容姿を勘案しても、おそらく、実際も、さっぱりとした気性でいらしたのだろう。 
今、『詩のこころを読む』を再読中である。
それにしても、ここ一年、どうも追悼動機の読書が多いような気がする。
|
 |
 先の日曜日、金沢二十一世紀美術館に行き、上記の美術展を鑑賞した。早いもので、秋に美術館巡りの日々を送ってから四か月たつ。 先の日曜日、金沢二十一世紀美術館に行き、上記の美術展を鑑賞した。早いもので、秋に美術館巡りの日々を送ってから四か月たつ。
ジャズLPをCD化する時、別テイクを追加することが多いが、それを「Alternative(オルタネィティブ)take」という。なので、今回のタイトルは、英語が全然の私でも意味がわかった。
今回の展覧会、「「工芸」の現代的価値を問いかける」というコンセプトで、布、プラスティック、髪の毛など日常的な素材を使って、手間をかけて造り上げる手藝・工藝の手法を基にした作品というのがゆるい共通点。布に一部刺繍して抽象画に仕立てたもの、手芸用品の寄せ植え的なスカート、細分化した布片を縫い合わせて巨大なパッチワークにしたものなど、膨大な創作時間がかかっているものが目につく。
しかし、それにしては、素材がすぐに色褪せる化繊だったり、安手のプラスチックだったり、長く保ちそうにもないものばかりで構成されている。本来的に、例えば、漆塗りなどの伝統工藝が持っている永遠性への希求を、これらの現代美術は拒否しているかのように見える。本来、時間をかけて制作するということは、その営為自体に永遠性への祈りが込められていると思っていたこちらとしては、そこが、逆に新鮮でもあったが、現代の美とは、徒労そのものをテーマにしている、あるいは、退廃的な虚無の美を演出しているにすぎないのではないかという危惧も心の中を駆け抜けた。しかし、そうした心配は旧弊な見方でしかないのだろう。現代アーティストたちは、そんな心配などさらさらしていないように見える。それこそ、食事をしたら用を足すように、作品を排出しながら前に前に駆けている。おそらく彼らにとって「クリエティビティー」とは「瞬間」の謂いなのである。労力はそれを固定化するための作業なのだ。
展示の中では、「TーRoom」なる白を基調とした無機的なお茶室空間の演出が電飾なども使って動きがあり、多くの人の興味を引いていた。確かに、この展覧会中の白眉だった。
地下では、二つの小展をしていた。
「河野安志写真展 きのう見た夢」ー実はこの写真展が最終日だ ったので、慌てて行ったのである。 ったので、慌てて行ったのである。
写真をコラージュし、それを白黒で複写し、直接、彩色した作品三十点ほど。すべてアナログの手作業で行われた手間のかかる手法だが、そのため、普通の写真展とは一線を画する現代アートになっていて、この美術館で展覧会をするのに相応しい。シュールレアリズムとマッドアマノの交錯した世界とでも言えば、わかっていただけるだろうか。
作者は、金沢でカメラマンとして活躍中だったが、食道癌のため、二〇〇四年四十二歳で他界した人。受付は親族が担当していたようだった。
隣の部屋では、「永澤陽一展 METAMORPHOSIS 変貌系」(金沢美術工芸大学教員作品展)というのをやっていた。昨年、金沢美大の専任教授(ファッションデザインコース)に就任した氏のファッションデザイン展である。余禄として鑑賞。
数百体にのぼるマネキンが群像的に置かれ、すべて違う衣装を身にまとっている。客は、その狭いマネキン間をすり抜けながら鑑賞する仕掛け。ファッションデザイナーの元衣装を、これほど間近に観たことはなかったので、まじまじと眺めたが、規格ものではないので、部分的には結構いい加減な縫製も目立った。また、中には、こんな大胆な露出では着る人はいないだろうというようなものも混じる。この中から、メーカーに気に入られた一部デザインが製品として量産化されるのかねと愚妻に問うと、いや違う、これはモーターショーのコンセプトカーみたいなもの。イメージを振りまいているだけで、世に出てくる新車とは別物と思った方がいいという答えが返ってきた。なるほど、よく判る喩えだ。
ホックをスパンコールのように並べたり、着心地悪そうなビニール素材を大胆に使ったりしているところなど、私のような門外漢には新鮮で見飽きなかったが、それにしても、女性の服は、ボディを見せたり隠したり、上下、変なところで切りかえたり……。体がでこぼこしているからどんなことしてもサマになる。
それに引きかえ、男の服のほうは、ジャケットとパンツで、情けなくなるほど普通、規格的だった。自分が着る服として全然面白くない。下手なのか、力が入っていないのか。はたまた、ファッション業界自体が男を無視しているのか。並んだ雌雄のマネキンの落差に、ちょっと困った。
最近、冬の中休みで、春めいた日が混じるようになった。この日もそんな一日だった。上はモコモコのファー、下はミニスカートでドスンと生足出しの、寒いのか暑いのか分からない格好の娘たちが押し寄せていたが、この子のファッションは今一歩だとか、この子はセンス抜群だが、ご面相は……とか、思わずチェックを入れてしまったのは、明らかにこの展覧会のせいである(笑)。
|
 |
|
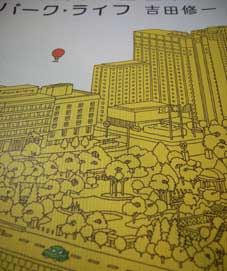 平成十四年、芥川賞を受賞した吉田修一『パークライフ』(文藝春秋社)は、日比谷公園を舞台にした公園小説(?)で、近くのスターバックスが重要な舞台となっている。ああしたお洒落で優しくて、でも、どことなくクールな都会生活のスタイルに、今のシアトル系コーヒー店はよく似合う。ある意味、シアトルコーヒー文化を表徴したスタバ小説(!)という言い方もできるのではないか。この作品は、そうした風俗をつなぎ止めた小説として、後世、名が残るかもしれない。これを、中上健次が、一九六〇年代後半、新宿の「ジャズビレッジ」に通い詰めたあの濃密な関係と較べるとその違いがよくわかる。 平成十四年、芥川賞を受賞した吉田修一『パークライフ』(文藝春秋社)は、日比谷公園を舞台にした公園小説(?)で、近くのスターバックスが重要な舞台となっている。ああしたお洒落で優しくて、でも、どことなくクールな都会生活のスタイルに、今のシアトル系コーヒー店はよく似合う。ある意味、シアトルコーヒー文化を表徴したスタバ小説(!)という言い方もできるのではないか。この作品は、そうした風俗をつなぎ止めた小説として、後世、名が残るかもしれない。これを、中上健次が、一九六〇年代後半、新宿の「ジャズビレッジ」に通い詰めたあの濃密な関係と較べるとその違いがよくわかる。
ところで、「喫茶店文化」とは何だったのだろう。あの頃の喫茶店にあって今ないものとは?
冴えない頭でちょっと考えてみた。誰でも思いつくような内容で、気の利いた説ではないけれど、せっかく考えたのだから……。
一、我々に本格的なコーヒーの味を教えてくれた。珈琲道伝道。当時、家庭と店では圧倒的な美味しさの落差があった。美味しいのを飲もうとしたら喫茶店に行かないと飲めなかった。
二、今は画一化されたチェーン店が全盛だが、昔は、一軒一軒、内装やメニューなどにお店の個性が発揮されていた。ある人は、その喫茶店を趣味がいいというし、ある人は嫌いという。その好き嫌いで、その人の嗜好が判ったし、自分が背負っている好尚を確認できた。
また、店に個性があるから、どのように使うかで選別もできた。例えば、私の場合、昔、よく使った香林坊交差点の「グラスホッパー」。ジャズ好きなのでどうせならジャズを流してくれているところがよくて、でも、基本的に、久しぶりに会う友人とおしゃべりするためだったので、ジャズ喫茶のように「大音量で黙って聞け。」ではダメだった。その結果の選択だった。
茶店通いには、マスターの趣味やこだわり、ひいては個人の人格の拡大としての店の雰囲気というものに惹かれる人も多かったように思う。規格内装、マニュアル接客では出せない部分である。
三、昔は、歌声喫茶、ジャズ喫茶、ロック喫茶などと、単に憩うだけの場所ではなく、その場所場所が自己主張していた。客は、発信される文化を吸収しにいったのである。大げさに言うと勉強の場であった。
四、その結果、集うお客さんには目的があった。目的が共通しているから、そこに交流が生まれる。今は客同士でつながりが生まれるわけがない。マスターから色々情報を仕入れたりする縦のライン、客同士の横のライン、両方あった。
五、今のスタバなどはお洒落に飲むといった感じが優先する。座席に座りながらも、自分自身、どこかで気取っている感じがする。自分の今風生活を演出する小道具としてのスタバという感じである。だから、年寄りには腰が落ち着かない。家で飲むのとは違うから、当然、ちょっとした気取りは、昔もあったが、昔のほうがまったり感があったような気がする。
と、ここまで書いてきたが、何だか、「昔はよかった」的な分析で、年寄りの繰り言のような気がしてきた。一律にこう言えるものでもあるまい。もう幾つか考えたような気もするが、このあたりで止めよう。
それより、これまで、これもかという具合に喫茶店は滅びつつあると書いてきたが、実は、思った以上に、どっこい生きているとも言えるということを最後に指摘しておきたい。
先日、日中、職場近くの郵便局に行く道すがら、意識して探したら、五〇メートルほどの間に二軒もあった。どちらも目立たない店構えでキャパシティも狭小である。日替わりランチをやっているので、それを毎日のように食べに来る固定客がいるのだろう。
こうなると、珈琲文化とは無縁の世界だが、私の分析の五あたりはしっかり押さえて、住宅地のまっただ中、ご近所の集会所、昼間の小料理屋さんといった役回りの個人営業でそれなりにご商売が成り立っているのだろう。
懐かしき喫茶店文化は、どうやら、こんなところに着地しているようだ。
|
 |
|
こうして、繁華街にある昔ながらの喫茶店はぐっと数を減らしたが、では、東京にいた時、利用した喫茶店は健在だろうか。もう四半世紀も昔の話だがと、ちょっと懐かしくなって、恐る恐るネット検索した。
といっても貧乏学生、お茶を飲むという不要不急の行為にお金を払うこと自体、勇気がいった行動で、お茶なんぞを飲んだら、その日の夕飯が貧弱になること必定。だから、実は、入り浸ったサテンなんて一軒もないのである。行ったことがある程度だと思っていただきたい。
同じアパートで仲良くなった中年の女性によく連れて行ってもらったのが、高級喫茶店「ウエスト」目黒店。ここは健在だった。本業は洋菓子舗で、その喫茶部という扱い。銀座本店が世間的には有名である。コーヒーは普通の倍の値段で、当時、自腹で行ったことはなかった。彼女は、教育の行き届いた店員さんがおかわりを淹れに来てくれ、何時間いても居心地がいいところが気に入っていて、気分がいい時や何かお祝いしたい時、学生の私たちを誘ってくれた。
自分でよく入ったのは、古本の町、神保町界隈。古本探索で足が棒になるので、これは、已むに已まれず入る。思い出すのは、大型書店「書泉」の裏通り「ラドリオ」。ここや、神保町交差点近くの「さぼうる」は当時から有名だった。昔ながらの造りで、ちょっと暗い店内は、ゴチャゴチャと年季の入った調度品が懐かしい雰囲気を醸し出していた。これらは今も健在。
残念だったのは、同じく神保町交差点、白山通り裏にひっそりとあった「李白」。和の中の李朝といったしつらえと調度が、当時としては珍しかった。アジアンブームになるずっと前の話である。ここは、つい最近引っ越して店をたたんだという。
あと、東京の喫茶店といえば、必ず出てくるのが、中野の「クラシック」。近くに下宿している友人に連れて行ってもらった。これも話の種みたいな物見遊山である。終戦時を思い出すようなバラック、BGMはSPかなと思わせる音で、ミルクの入れ物はマヨネーズの赤い蓋、水はカップ酒の容器だった。これにはびっくりした。ここも、先代の死後、娘さんが後を継いでいたが、その方も亡くなり、去年閉鎖したという。
そういえば、ジャズ喫茶のオヤジという立場からジャズ雑誌に健筆を振っている某氏の店も、最近ライブハウスに鞍替えしたそうだ。古き良き文化としての喫茶店の灯は、今まさに消えようとしている。(つづく)
|
 |
金沢市の繁華街、片町の老舗喫茶店「ぼたん」がこの二月十四日閉店した。女主人の御高齢(九十一歳)が理由だという。惜しむ声も多く、地元新聞でも大きく取り上げられていた。
私も何度か行ったことがある。ソファなど、傷んでいるといっていいくらいの古さで、若い頃、ここが金沢の喫茶店草分けの一つだからという社会見学的な気分で入ったのが最初だったような気がする。その後、これといった喫茶店がなくなって、消去法でここを利用した。最近は、そうした利用のされ方で、なんとか生き残ってきたように思う。
古くからの喫茶店といえば、昭和のモダンボーイ鞍さん(故人)がやっていた柿木畠の「金沢喫茶村」がすぐに思い浮かぶが、あそこが閉店してからもう十年以上たつ。老舗で今もやっていてるのは、同じく柿木畠の「芝生」、香林坊の「ローレンス」、竪町「犀せい」くらいのものである。
世に喫茶店文化というものがあったとしたなら、我々の世代は、その末端くらいに位置している。安保世代より下なので、ジャズ喫茶に入り浸りという、「まっただ中」の世代ではないが、高校時代、友達との待ち合わせなど、何かといえば喫茶店を使っていた。今の高校生が純喫茶なんかでコーヒー飲んで友達待っている図は想像できない。
あの頃、「禁煙室」(ノー・スモーキング・ルームということで、NSRと略して言っていた)という地元資本の喫茶店が全盛で、あちこちに支店を開いていた。そこで雑談に何時間も粘ったものだ。もちろん、喫茶店だから煙草はOKのお店なのだが、それを知らぬ煙草吸いの客が、店の前で慌てて火を消していたという話は、当時、誰でも知っていて、この店を語ると必ず出る話題だった。
喫茶店文化に翳りが見えたのは、マクドナルドやミスタードーナッツなどのファーストフード店が、竪町・香林坊に進出してきたころから。コーヒー一杯の値段で、ミスドはドーナッツ一個付くから、そっちのほうがリーズナブルということになった。待ち合わせはこっちで。それに深夜までやっているので、飲み会の酔い覚ましにも最適。これで個性のない店は一気に潰れた。息の根が止まったのは、ドトールコーヒーなど安価なスタンド型コーヒーショップチェーンが開店した頃。その後、中央で話題のスターバックスコーヒーが鳴り物入りで押し寄せてきて、これはもう死者に鞭打つ状態となった。
この流れ、飲み物の視点から大雑把に見ると、旧来の喫茶店が日本の珈琲文化を育てたが、最初、不味いけど安いコーヒーに押され、その後、安いがそれなりに美味しいコーヒーの驚異に晒され、今は、お洒落っぽい米国式バラエティ味付けの付加価値路線が流行中という具合になると理解してよいかと思う。(つづく)

|
 |
|
何年くらい前からだろうか。提出された問題集に「名無しの権兵衛」が大量に出てきたのは。
昔もうっかり者はいたものだが、先日、手をつけたばかりの問題集を提出させたところ、一クラス平均六名は無記名だった。小学校の時、そうした教育がないがしろにされているからかなと思う。鉛筆の持ち方変な子が、クラスの三分の一(!)もいるくらいだから。
そこで、こっちは、マジックで、でかでかと「名無し」と書いて返す。一年間、それを見て嫌な思いをしてもらおうというのが趣旨である。
こんな時、未提出扱いになるわけだから、これは私ですと後で申し出るべきものだが、最近、いつまでたっても言いにこない生徒が混じるようになった。
かつて、実際にあったやりとり。
君はまだ提出していないねと、提出状況チェックすると、「出しました。」と言い張る。では、検印があるか見せなさいというと、出してきた問題集は、案の定、名無しであった。それじゃあ未提出と同じでしょうというと、「でも、出しましたから。」と悪びれずにいう。出したという事実は認めろというのである。感覚の違いにちょっとびっくりする。
ノートの名前も、表紙に書いていないものが時々ある。あっちこっち探すと裏表紙をめくった下あたりに小さく書いてあったりする。
そんなこんなで、点検作業は、昔に較べて手間が増えた。
そこで、こちらの予防策は、その場で、表紙や所定欄に書かせることである。ノート提出の時も一言添える。これ、四月中に結構する作業。
小学生じゃあるまいしと、最初は情けなく思っていたのだが、言わないと、結局、こっちが大変になる。よく仲間内でいうのは、悪気があるのではなく、今の子供は、常識や道理を知らないだけ。だから、いちいち言ってあげないといけないという理屈。そんなんじゃあ、人間育たないでしょうと、ちょっと納得しかねる部分もあるが、そう思って対応するしかない。
愚痴っていると、では、あなた自身はどうなのと反論がきそうだけれど、ええ、もちろん、ちゃんと書いていますよ。腰が痛くて、それで気が散って、見事に注意力散漫人間になっています。自分で自分が、全然、信用置けない。そこで、このところ、身の回りのものすべてに書いてます。別に書かなくてもいいのではと思われる小物にまでせっせと。職場で使っているもの、持ち運ぶものにいたっては、これでもか、これでどうだ状態。自分で言うのもなんだけど、ちょっと尋常ではない。でも、それくらいすると、結構、置き忘れても戻ってくる。
紙もの以外はシールを貼っている。ビニールを上からもう一度貼るタイプの「見出しタグ」。閻魔帳にクラス名などを書いて耳にする例のやつである。これだと表面に紙が露出していなので丈夫なのだが、愚妻からはダサイと大不評である。でも、この際、みっともないより実用本位。
と言うわけで、名前書きに関して、私は完全に模範生である。
問題の、名無しの生徒たち。これって、つまり、生き馬の目を抜くようなところでは、ちょっと生きる力に欠けているということになる。まあ、いい歳になって、重大な忘れ物をして痛い目にでもあえば、ちゃんと身につくのだろう。
本人はそれでいいとして、子供を教えているこっちは、以後、ずっと言い続けなければならないかといえば、実はそうとも限らない。教育はゆっくりながら是正する力をもっている。
例えば、発達の「達」の下の横棒が二本だけで「幸」になっている生徒さんが大量にいたのは一昔前のこと。正しい字を見て、なんだか一本多いような違和感があると言った子がいたくらいひどかった。このまま、そんな世の中になるのではないかと恐れていたが、ここ五六年、ぴったりとそんな生徒はいなくなった。おそらく、この話が小学校国語教育の方に行って、注意して教えるようになったのであろう。ある意味、見事な教育の成果である。
名無しの件も、こっちがギャアギャア言えば、十年後くらいには期待できるかもしれない。
ただ、それまで、こっちは、せっせと「お〜い、お前ら、ちゃんと名前書いてあるか確認しろ〜。」と、喚くしかなさそうである。
あ、でも、そのころには定年退職か。
|
 |
|
 荷風の従兄弟、杵屋五叟の次男で、荷風の養子となった人による回想記。去年の六月の刊行。子供の頃、従兄弟二人の間で養子縁組が決まっていたが、仲違いなどで、廃嫡問題がおこるなど、決して順調ではなかった立場の人である。荷風と一緒に暮らした期間もきわめて短い。 荷風の従兄弟、杵屋五叟の次男で、荷風の養子となった人による回想記。去年の六月の刊行。子供の頃、従兄弟二人の間で養子縁組が決まっていたが、仲違いなどで、廃嫡問題がおこるなど、決して順調ではなかった立場の人である。荷風と一緒に暮らした期間もきわめて短い。
そうした人だから、一部には、あまりよく言わない人もいて、実際、荷風の文献を調べていると、はっきり悪く書いてあるものもある。著者も自分は当時「悪者」扱いされたとはっきり書いてある。市川の荷風最後の家に移り住んだ当座、マスコミや近隣の人から白い目で見られていたという。血が繋がっていない、荷風自身、最終的に望んだ後継者ではなかった、著作権などのお金の問題が絡み世間からやっかみを受ける、など、妻子ともども大変な目にあったようだ。
彼の職業が飲食業で、文学とは縁のない一般人であったことも 彼が世間から軽んじられた原因になっていたかもしれない。関係者からしてみれば、文学をよくも知らない若造が、法律的に嫡子扱いになっているだけで……という具合に映っただろう。
ここに語られる荷風を直接知る友人、作家、編集・出版関係者、みんな生存していない。作者は、ようやく、自分の立場を語ってもよいと思ったのだろう。関係者が生きている時に語れば、何をどう言ったって非難する人がいる。だから、これまで故意に口をつぐんでいたのだろう。
彼は彼なりに、荷風が残したものを守ろうとした。市川の家に今も住み続けていることにも驚いたが、小改造をしただけで、書斎もそのままにしている努力にも敬服した。彼は充分誠実に守るべきものを守ったと思う。
親が荷風の養子になどと決めなければ、ごく普通の人生を歩んでいたはずである。一人の文学者が亡霊のように彼の人生を死ぬまで決めてしまった。自分の人生の大部分を荷風荷風で費やさねばならない。そんな大変な人生を歩まされた人である。
昭和七年生まれ、今年七十四歳。荷風死して既に四十七年たつ。彼は、浴びせかけられた非難を、一生かかって、態度で反論しようとしたのではなかっただろうか。そして、それをみんなに知ってほしかったのではないだろうか。読んでいて、それを強く感じた。
おそらく、年齢的に、この本が、荷風を直接よく知る人の最期の回想記になるかもしれない。五十年近くの歳月は人を挨たない。
後は余瀝。
私が気になっている人物について、文中に触れられていた。
当時、全集出版を岩波に決めた永光に対し、これまでの故人とのつきあいを無視した独断だと非難した中央公論社の故嶋中鵬二が、晩年、尋ねてきたという話がさらりと書いてあった。詳しくは想像するしかないが、その時すでに命短いことを予感した嶋中が和解と別れの挨拶に来たのではなかったか。作者は、荷風文学が読み継がれるということにおいて、自分の決断は間違っていなかったとはっきり断言しているが、これは、結局、中央公論社は経営破綻したではないかと揶揄しているようなニュアンスで受け取れる。嶋中は、当時はいろいろ取り巻きがいたからとその時言い訳したそうである。
鵬二は、著名な先代社長、嶋中雄作の息。谷崎ら多くの文学者と交流があった。若くして社主になり、深沢七郎『風流夢譚』事件で右翼に刺されたことでも有名である。晩年には、会社が左前になっていく事態も直接見つめねばならなかった。彼を知る出版関係者の筆になる内幕記はいくつか散見されるが、その文学交遊も含め、全体像を掘り起こした人物伝が出ないものか。私は密かに期待しているのだが……。
 (今日はバレンタイン) (今日はバレンタイン)
|
 |
|
アニメ「ちびまる子ちゃん」で有名なさくらももこのエッセイを三冊まとめて読む。急に、さくらももこを読んだのは、入試の難しい文章を読むのに飽きたからである。この時期、字を見るのがイヤになって、本を読むペースががっくりと落ちる。軽いエッセイで、ちゃんと読んだことない人という基準で、図書室の書棚を眺めていたら、ちょうど目の高さに、彼女の本がたくさん並んでいた。
『さくら日和』(集英社)は、『もものかんづめ』(集英社)など一連のシリーズ共通の装丁と内容。『ももこの二十一世紀日記』(幻冬舎)は、携帯サイトの文章にイラストを書き下ろしたもの。『まる子だった』(集英社文庫)は、子どもの頃の思い出話。
一九六五年生まれ、今年四十一歳。私より少し下の世代である。あのアニメも、当初は、昭和四十年代あたりの静岡県清水市の生活が色濃く反映されていたように記憶している。
その、大人になったまる子ちゃんが書いている「文と絵」だと思うのが一番分かるし、購買層のほとんどもそう思って買っているように思う。『まる子だった』の表紙カバーの折り返し、作者紹介の顔は、そもそも、ちびまる子のイラストが描いてあるくらいなのだから。これも一つの戦略である。
『さくら日和』では、彼女の息子が、母をさくらももこではないかと疑っていて、それをなんとか誤魔化している様子がネタになっていたが、『二十一世紀日記』のほうでは、もう知っていて、子どもとコラボレーションして絵本を出す話が書いてある。子どもの成長を、読者も温かく見守る構図である。
実は、家族とのつきあいをほのぼのと書いているエッセイ、結構好きである。昔、佐藤愛子の「娘と私」シリーズをゲラゲラ笑いながら読んでいたので、あれと同じような親近感を感じた。かあちゃんが物書きなので、単なる一般の子どもであるはずなのに、自分の言動や失敗、世の中の人みんな知っているという変な立場。イヤだろうなあ。
中に、アニメ「ちびまる子ちゃん」の脚本募集の文章があった。もう、アニメに関しては、原作者の手を離れているようだ。最近、アニメは見ていないから分からないが、「静岡のあのころ」というモチーフは、テレビでは希薄になっているのではないだろうか。
彼女の本、時に入るイラストが文章をうまく補完していて、それで、また楽しめる。そんな彼女の、肩の力が抜けた文章読んでから、自分の、この日記を読むと、字ばっかり、漢字ばっかりなのに、ちょっとゲッソリした。ブログでもそうだが、絵があって字もあるほうが、今の世の中、標準的な感じなのだ。今はそんな文化。自分もちゃんとそれに慣らされていることを感じる。
彼女、売れっ子になってだいぶたつ。もう、現役女子高校生に大人気ということはなくなった。図書室にいるので、そのあたりの流行具合はどことなく判る。漫画「ちびまる子」愛読世代が、そのままお客さんについて、一緒に歳をとっているのだろう。
|
 |
 今日から、イタリアトリノでの冬季オリンピックが始まった。こちら時間早朝の開会式をテレビでながら鑑賞。向こうは夜である。オリンピックは、本当に人生のお楽しみである。夏冬交互に二年に一度、もうどれがどの五輪だか記憶はごちゃごちゃだが、ニッポン頑張れで、スポーツに別段関心のない私のようなものでも、テレビを観るのが楽しみになる。 今日から、イタリアトリノでの冬季オリンピックが始まった。こちら時間早朝の開会式をテレビでながら鑑賞。向こうは夜である。オリンピックは、本当に人生のお楽しみである。夏冬交互に二年に一度、もうどれがどの五輪だか記憶はごちゃごちゃだが、ニッポン頑張れで、スポーツに別段関心のない私のようなものでも、テレビを観るのが楽しみになる。
人生が長くなると、桜を見てまた歳が巡った感慨にふける心が静かに沈潜するが、巡るオリンピックにもそんな感慨がわく。
それにしても洗練されている。出し物一つ一つが見たことないアトラクションで、そのため、新鮮な驚きがある。人間を使った壁面アートや火を噴くヘルメットのスケーターなどが映像的にインパクトがあった。トリノではあの出し物があったねと、観た人の心に印象を刻んでもらおうという意欲を感じる。出し物と出し物の連続性もよく考えられていて、押しつけがましくない程度に人類の平和を訴えるモチーフを入れたかと思うと、サラリと自国をPRしたり、演出が上手い。入場し終えた選手にはベンチが用意されていて、疲れなくて好評だったという。これは、つまり、ハケた人員の処理がうまいということ。
音楽は、懐かし路線。入場行進は、全世界誰でも知ってる懐かしい一九七〇、八〇年代のノリのいいヒット曲を使っていた。他の出し物の選曲も親しみやい。
また、カメラワークが芸術的だったことも印象的だった。ズームアウトしながら出し物を巨大な鉄骨の五輪の輪の中に撮して遠近を強調したり、五輪旗入場をアップで撮して、通り過ぎると向こうにその鉄骨五輪が五色に輝いているのが見えたり。考えられた構図的なショットが多かった。
デザインの国だから、やっぱり、洒落ているんだなあと思いながら見ていたのだけれど、テノール歌手パバロッティがオペラハウスを模したステージから出てきた時にハタと気づいた。
イタリアはオペラのお国柄。関係者にしたら、巨大劇場でオペラ「冬季五輪」を上演しているみたいなものだ。手慣れているはずである。
どこかの国であった昼間の田舎臭い開会式とは大違い。
|
 |
|
先月三十日付「朝日新聞」朝刊に、谷崎潤一郎の旧居「後の潺湲亭(石村亭)」が、人数を限って一般公開するという記事が出ていた。昔、訪れたことがあるだけに、懐かしい思い出がよみがえった。
谷崎潤一郎は、昭和二十四年から昭和三十一年まで、下賀茂神社糺(ただす)の森横にある見事な庭園つきの日本家屋に住んだ。この家を、南禅寺近くの「前の潺湲亭」(現存せず)に対して、「後の潺湲亭」という。谷崎は、ここで『鍵』『夢の浮橋』『新訳源氏物語』など、戦後の代表的な作品を執筆した。
「潺湲(せんかん)」とは、水の流れゆく様をいう。「潺湲として流る」などというフレーズが漢文にはよく出てくる。売却の際、谷崎は、分かりやすい「石村亭」という名を譲渡者に与えた。新聞は見出しで「せせらぎ亭」と書いているが、そんなのは勝手な読みかえで、違和感があった。
高校時代より谷崎を耽読し、大学では「戦後の谷崎」を研究テーマに選んだので、研究対象作の多くを執筆したこの潺湲亭は、いわば私にとって憧れの場所だった。
ただ、論文は現地に行かずに済ました。どこかの会社所有になっており、入れないことを知っていたし、単純に、学生の身分、京都までのお金がなかったのである。
その後、社会人になり、経済的に少し余裕が出た、今から二十年ほど前、重い腰を上げ、ようやく取材旅行に出かけた。下賀茂のこの家、谷崎の墓、それに墓所近くにお住まいの息子の嫁、颯子のモデルに当たる渡辺千萬子さんとお会いしたりした。
当の石村亭は、下賀茂神社参道にはいると、捜すと言うほどのこともなくすぐに見つかった。写真で見ていた入り口の様子からして、こんな佇まいだろうと想像する通りの場所にそれはあった。入り口に縦長の石仏が出迎える。通常、門は閉まっているはずだが、この時は、偶然、開いていたので、そろそろと中にはいる。思いがけず管理の方がいて、声をかけて許可をもらって、簡単に庭だけ見学させてもらった。
ここは、『夢の浮橋』の舞台になったところであり、単に住んでいたという以上の調査価値がある。物語は、亡くなる父が後妻を息子に託すという話で、『源氏物語』を下敷きに、まだ若い妻松子を誰かに託さねばと考える谷崎の主体的願望が綯い交ぜになって紡がれている。特に、庭の離れが妻と息子の秘密の場所として妖しい存在感を示す。実際の庭、離れの配置を、後で作品と照らし合わせてみたが、ほぼそのままだった。
谷崎がここを去る時、松子夫人の同級生の夫が、日新電機(左京区)の役員だった縁で、この会社に譲ったという。新聞によると、いまだにこの会社が単独で営々と管理を続けているとのこと。谷崎の、できるだけこのままでという希望を受け入れ、現状維持に、毎年、かなりの維持費をかけているようだ。
昭和三十一年の売却から今年でちょうど五十年になる。一地方会社が、年数回の接客に利用するだけのために、この古風な家を維持するのは、なかなか大変なことだ。
WEBで会社からのお知らせを見ると、社内にゆかりの品や詳しい資料などは残っていないようである。当時の事情に詳しい人も、もういないという。
文面から推察して、強固な使命感を持っての運営ではなかったのが意外だったが、ある意味、そうした「遺産を守らなければ意識」がなかったからこそ、例年通りの維持管理費計上で、淡々と処理してきたのだろう。それが逆によかったのかもしれない。
谷崎ファンとして、久しぶりに新聞で彼の話題がでたので、ちょっと嬉しくなった。

(門にある石像 「人と文学シリーズ「谷崎潤一郎」より転載)
|
 |
東京の鍋の話をしたので、今度は金沢の食の話を……。
ネットで「金沢」と入れて検索した話は二度ほど書いたが、そこで、金沢市内のグルメリポートをしているサイトを何件も見つけ、「お気に入り」に追加した。お仕着せ記事と一番違うところは、良い悪いがはっきり評価してあるところである。
自分の行ったことある店の記事を読み、自分の印象とその人の印象を照らし合わせると、印象記書いた人がどんな嗜好の人か判る。そうした点を考慮に入れて、車ですぐに行ける距離のお店をピックアップして、記事を詳細に読む。みんないっぱしのグルメリポーターである。料理の印象だけなのは、情報として利用しにくい。詳しく、所在地、駐車場の有無、HPのリンク、店の雰囲気など、外延的な情報も詳細に紹介してあるサイトが役に立つ。
日頃の外食は、どうしてもいくところに固定しがちである。そこにそんな店があることは知っていても、どんなところか判らず、ためらわれることもしばしば。そんな不安感がこれでなくなる。何軒も、行ったことがない店を見つけてメモした。今後、春先まで、ちょっとしたグルメな気分を味わえそうである。
私のような人は多いと見えて、小さな食堂が好印象で紹介された途端、そこのHPのアクセス数が急増したという。印象記を書いた人も、その店の売り上げに貢献できたかもしれないと喜んでいる文章が次の記事でアップされていた。
だけど、その逆もあり得る。ちょっと拍子が悪くて、悪印象を持った人が大々的にそう書いたら、店の浮沈にかかわることになる。悪意あるものなら訴訟も出来るが、印象記で低評価程度なら喧嘩も出来ない。お店は、店内で料理の皿撮っている素人さんが一番怖いのではないだろうか。
そんなグルメブログを見ると、ラーメン無風地帯と呼ばれていたここ金沢に、近年、大挙、新規ラーメン屋が出来、過当競争に陥っている様子がほの見えるし、有力カレーチェーン店のライバル心むき出しの争いが、大学生さんあたりの格好の雑談ネタになっている様子もわかる。カレー屋さん二軒並んで商売しているのだから話題にならないわけがない。
学生食堂タイプの、おかずを選べる定食屋が増殖しているのも見 てとれる。実際、私も、数年前出来た車で十分ほどのそんな店によく行く。ヘルシーを心がけて皿をとると、外食だと思われないほどお腹にやさしい献立が出来上がる。煮魚、煮物、菜っぱのおひたし……。 てとれる。実際、私も、数年前出来た車で十分ほどのそんな店によく行く。ヘルシーを心がけて皿をとると、外食だと思われないほどお腹にやさしい献立が出来上がる。煮魚、煮物、菜っぱのおひたし……。
油もの、和もの、色々選べて、学生・勤め人以外に、家族連れにも大好評の様子である。子供はハンバーグ、お爺ちゃんは魚という風に、どの世代も食べるものがある。飲食業界、ニーズに応えられていないところを見つけて、その隙間をついて、ちゃんと大繁盛を勝ち取っているようである。
県外の人には「金沢=魚が新鮮」というイメージも強固にある。北陸は回転寿司のグレードが高いということは聞いていて、そうだろうとも思ってはいたが、大都市圏では、一皿百円均一なんてところもあるようだ。そんな所では、回転=安物というイメージがあるらしい。もちろん、こちらでも大将が握る本格的なところよりはずっとリーズナブルだが、それでも一皿千円近いクラスのものも、結構、平気で廻っている。回転でも、ちょっと贅沢に食べると、びっくりするお値段になる。高額にならないように強弱つけながら食べるのが、こちらの貧乏人には常識の食べ方である。
だから、こちらで評判の某回転寿司屋さん、東京で店を出しているが、そこは回転しないのだという話をネットで読んで、なるほどと思った。
おそらく同じ食材(ネタ)だろうけれど、お客に同じお金出してもらうときに、回転では承知してくれないのだろう。ご商売としてよく考えられている。
そういえば、学生時代、東京のスーパーの特売で買ってきたお刺身、不味くて損したと思ったなあ。美味しい魚は、それなりにお金を出さないとダメらしい。こちらは雪に降り込められる土地柄。苦労も多いが、美味しい食の代償だと思えば諦めもつく。
それで、ちょっと思い出した。降り込められ話題のほうなので、ちょっと脱線だが。
先日、「伊勢物語」の授業で、老母から息子宛てに急に会いたいという手紙が届く章段をした。有名な、
世の中にさらぬ別れのなくもがな千代もといのる人の子のため
という和歌が最後に記されている第八十四段である。
生徒に「押し迫った十二月、緊急でもなさそうなのに、なぜ、急に会いたくなったのか、その時の母の気持ちを説明せよ。」という質問をした。答えは、昔は数えで年齢を数えるから、年越しで歳を重ねることに気づき、老いを自覚したからというものなのだが、ある生徒は、雪で閉じこめられて、内省的になるからというような答えをしていた。なるほど、新説である。でも、「それは、ちょっと北陸的な発想かもしれないねえ。」と、一応、不可ということにした。京都あたりは寒いけれど雪はほとんど降らない。
ちゃんと「風土」は、人生経験の少ない高校生でも、その発想に深く入り込んでいるものだ。それが当たり前ではないということを知らないからこそ、逆によくわかる。
さて、今夜は、これを書いたので、最近、ちょっと行かなくなっていた、ちょっと高級風(?)の某回転寿司屋さんに行ってきた。アラ汁がサービスに付き、割引券も使ったので、とってもリーズナブル。ポイントも満了し、次回金券として使えることになった。
北陸在住の小市民、プチ満足の図。
|
 |
|
酒の話をしたから、次は鍋の話となる。
昔、東京で私学の非常勤講師をしていたころ、現職の先生に、どぜう鍋を食べにつれ行ってもらった。由緒溢れる建物で、こってりした味噌仕立ての甘い割り下でいただき、下町情緒を満喫した。
先日、そのお店に行った金沢の方が、自分のブログに店内外の写真を掲載しているのを見つけ、懐かしい景色と二十数年ぶりに再会 した。最初、どこかで観たことがあると思い、じわっと記憶の底から湧いてくる感覚に心揺れるものを感じた。あのころと、全然、変わっていない。店の名前、何処にあるか、どんな由緒があるのか、今ごろになって詳細を知ることとなる。若い頃は、連れて行ってもらったこともあり、へえ、古いお店だねえ程度で終わっていた。金沢では、泥鰌(とじょう)を蒲焼きにして串で食べる習慣があり、珍しい食べ物と思わなかったせいもある。やはり、東京では超有名な老舗で、当時、我々のような地方出身の若造に、江戸情緒を味わわせたいと、先輩方がわざわざこの店を選んでくださったということがわかる。 した。最初、どこかで観たことがあると思い、じわっと記憶の底から湧いてくる感覚に心揺れるものを感じた。あのころと、全然、変わっていない。店の名前、何処にあるか、どんな由緒があるのか、今ごろになって詳細を知ることとなる。若い頃は、連れて行ってもらったこともあり、へえ、古いお店だねえ程度で終わっていた。金沢では、泥鰌(とじょう)を蒲焼きにして串で食べる習慣があり、珍しい食べ物と思わなかったせいもある。やはり、東京では超有名な老舗で、当時、我々のような地方出身の若造に、江戸情緒を味わわせたいと、先輩方がわざわざこの店を選んでくださったということがわかる。
行ってよかった。働き始めたばかりの薄給の身では、それなりにお金のかかる料理屋さんに自分一人では行けない。いい体験だった。
大学時代、せっかくの東京、あっちこっち覗いて歩こう、大学と下宿の往復で終わらせないようにしようと、かなり意識して動いた。あの発想は正解だった。意味が分からなくてもいい。気づくのは、大人になってからで充分である。後でいろいろ理屈がつく。まず最初に体験がないと始まらない。どぜう鍋文化なども、今の今、ネットで調べて勉強になった。体験からえらく時間たっているが、体験があったからこそ興味も湧く。
その店のHPに、泥鰌の旧仮名遣いは、本当は「どじ(ぢ)やう」であって、「どぜう」は、縁起をかついで三文字にした当時のご主人の造語だと書いてある。このトリビアネタは、一応、国語教師なので知ってはいたが、このお店が発祥らしい。
元気になって、もう一度行きたいなあ。今の季節、体が温まりそうだ。と、美味しそうな鍋のパソコン画面見ながら、安酒をグビリ。
かように、私の考えは、何事も「まず一歩踏み込もう」である。パソコンもそう。DOS機を長年使っていたので、ウインドウズになって、全然、判らない時期があったけど、まず、買えばいいと思って、ポンと98ノートを買った。買った以上、弄る。弄っているとすこしずつ判ってくる、職場で、人様から聞いて必要最小限だけ触っていては、絶対、うまくならない。
パソコンをよく知らない人は、大抵、職場で使っているだけで、自分用を持っていない場合が多い。関係のない設定の箇所なども、暇々に覗いて、どこにどんなコマンドあるかを知る、それが後日役に立つ。
カメラもパソコンも、機械ものは、まず買ってしまう。それで世界が広がる。
東京時代、歌舞伎も、大学の先生のご厚意で引率していただき、初めて観て、楽しく、思ったよりよく判るので、アレルギーがなくなった。しゃっちょこばる必要のない楽しい娯楽だということがよく判った。あれも、あの時、行きたい人と言われて、ハイと手を挙げたから。
でも、この発想、どうやら、父親からの遺伝らしい。
一見前向きの、この態度。問題もある。家族で一番、変な電話に引っかかりやすい人物は、家族の満場一致で老父であるということになっている。よく言えば、好奇心旺盛なのだけれど、このごろよくかかってくる怪しい勧誘の電話に、即、乗って、面白そうですから資料送って下さいなんて受け答えしているらしい。
危ない危ない。大丈夫かなあ。
(写真は「金沢ときめき浪漫」サイトより(縮小の上、一部切り取り)
|
 |
|
 私は大酒飲みではないと断っておいて……、お酒の話をします。(笑) 私は大酒飲みではないと断っておいて……、お酒の話をします。(笑)
もともと、私は夏にビール一缶程度の晩酌をする人なのだが、冬は、なんと言っても日本酒である。三十歳すぎた頃から日本酒のおいしさを知り、プチ日本酒党になった。但し、冬季限定。全国の銘酒に詳しいわけではない。ここ北陸は酒が旨いので、その飲み比べが楽しい。それで充分な人である。
昔、栂池スキー場の、お客が一升瓶を手土産で持っていくのが慣例になっているペンションに連れて行ってもらって、そこで、酒を酌み交わしたことがある。日本全国の酒が集まってきて、自分らの酒は飲まず、他国の酒を飲むというシステム。それで、飲んだことがない地方の酒が飲める。面白いやり方である。きっと酒飲みのオーナーが考えついたのだろう。
あの時、一本目は広島の「加茂鶴」だった。これは旨かった。後年、広島に行った時、探したくらい。広島市内の蔵ではないので、すぐに見つからなくて意外だった。あの夜、旨かったので興に乗って、岐阜の酒も開けたのだが、これが大ハズレ。不味いのなんのって、どぶのような臭いがした。いっぺんで座はお開きになった。明らかに水が悪い味である。日本酒は水が命ということを今更ながら実感したことだった。
あの時、県外の人が北陸の酒を有り難がる気持ちがよくわかった。以来、地元の酒ファンである。
普段飲みは、富山の「立山(本醸造)」。下から二番目のランク。一番下は「普通酒」というのがあるが、これは、あまり美味しくない。もう数百円でぐっと旨くなる。高い酒で美味しいのはごまんとあるが、安くて美味しいのが本当の酒だなんて嘯いている。普段使いでコストパフォーマンスがいい。
ちょっぴり舐めるなら、以前紹介した、新潟の「菊水(ふなぐち)」。麹の香りたっぷり。超甘口である。
どちらかというと、磨きに磨いた大吟醸は、美味しいには美味しいのだが、あっさりしすぎで、金沢弁で言うところの「愛想(あいそ)もない」のである。もちろん、この意見に、高級酒など飲めないという僻みが入っているのは否定はしませんが……。有名な新潟の「久保田」とかも、もちろん、うまいけど、手に入らず、割烹のメニューにあった時頼んで、高いお金取られる。だから、ちょっと敷居が高いイメージがある。
今年に入って、白山市の「天狗舞」を既に飲んだ。これも全国的に有名な銘柄。いつものように下から二番目のランクで試したが、まあまあよし。おそらく値段に比例してうまくなるタイプの蔵ではないかと思う。
同じ白山市では、「菊姫」「万歳楽」「手取川」がある、特に「菊姫」「万歳楽」は、旧鶴来町の蔵元で、昔、五年間、仕事で通っていた町なので、毎日のように酒蔵の横を通った。「菊姫」は、近年、全国的に名が知れ渡って、蔵元は、大工場を建設して大発展。町一番の大きな建物になった。首都圏での口コミの力は地域経済に大した影響力を行使する。
先日、愚妻が友人と妙高にスキーに行き、そこの酒屋で、新潟の「吟醸越乃雪月花(しぼりたて生)」(期間限定)、「毘(びしゃもん)(にごり酒)」、「菊水(一番しぼり)」緑缶を買ってきてくれた。今はこれらをちびちび飲んでいる。初めて飲んだ「越乃雪月花」は、わざわざ少し濁りを残し、麹の香りの強い、でも、ふなぐちよりは甘味を抑えた旨口タイプだった。
大都市圏と違って、地酒の品揃え豊富な酒屋を、わざわざ探し出してくる必要がない。地元の酒屋で地元の酒を選べばそれで正解。こちらで、うまくもない全国銘柄の酒をわざわざ買い求める人はいない。
ああ、酒が旨い土地に生まれてよかった。
大都市圏の酒飲みの人、羨ましいでしょ?
(今回は、グラス片手に酔っぱらいながら書いた地元の酒自慢。それだけの内容です。そうそう、それと、私が飲んでいるのは四合瓶です。念のため。)

(金沢小立野「福光屋」酒蔵にて)
|
 |
|
これも、ある意味、男女もの。
『ダーリンは外国人』シリーズの三冊目。このシリーズ、ベストセラーになって、すでに百万部だという。根強い人気で、図書室でも借りる子が多い。
前二冊は、外人と結婚して感じた文化の違いを面白可笑しく取り上げていたが、今度は、語学オタクの旦那さんと共著になって、言葉からみた比較文化論である。(もしかしたら、税金対策かも?)
日本語の「と」はずるい言葉だとか、日本人は受身を何にでもつかって曖昧化させるが、外国では能動性・積極性が強調されるので、多用は戒められているといった話題が、夫婦のやりとりの中で進められていく。
「切る」は英語で「カット」。どうやらカ行は切断のイメージと結びつきやすいらしい。
「架空の言葉で、MALとMIL、どっちかが大きなテーブル、どっちかが小さなテーブルです、大きいのはどっち?」という質問に、八割以上の人がMALと答えることから、音のイメージに人類共通の傾向があるという話なども、世界的視野で言語を考えることが少なかった私には興味深かった。
こんな漫画なら、ためになっていい。
もともと、夫婦のやりとりものというのは、永遠の題材で、全人類的に親しい。だって、毎日喋っているのだから、嫌でも感ずるところがある。性別が違う、年齢が違う、出身地が違う、育ちが違う、違う違う同士の日々のやりとり。驚きの連続である。彼女の場合、相手が外国人ということで、その振幅がもっと激しかったハズで、そこをうまくトピックにしている。漫画自体も楽しいし、旦那さんの髭ズラ、本物とそっくりだけど、彼女の本当の才能は、そうしたやりとりの中から、大事なことを見つけ出す力である。
|
 |
|
薬師丸ひろ子、仲間由紀恵と、女性話題がつづいたので、調子に乗って、今度は「カップル論」(?)。
昔、肥っていて今は痩せている林真理子が、FM番組「サントリー・ウエイティングバーAVANTI(アバンテ)」の中で語った話がある。
私のような才能がある女は、貴方は文才あるとかなんとか言われても、なんとも思わないけれど、肉体を褒められると、コロッといくと思う。だから、スタイル抜群の女性を口説くのだったら、容姿をほめても女はなんとも思わない。ボディを褒めるのではなく、知性を褒めるといい。あっけなく陥落するはずだというのである。
「自分は才能ある女」というのが大前提の話で、そこがちょっとひっかかるけど、理屈としては通っている。単純にして卓見である。
これを聞いていて、その少し前に、やはり同じ番組でやっていた話と似ていると思った。
生物学的に言うと、優秀な遺伝子を持つものは、好きな相手にその部分については多くを望まないのだそうである。美女は、相手が美男子であるより、知性など、それ以外の魅力でその人が好きになるそうで、逆も真なり。美女と野獣、ハンサムとおかちめんこカップルの誕生である。
出っ歯は出っ歯より受け歯が好きということですね。でも、そうしたら、二人の間に、上唇も出て下唇も出たワニのような子が出来るかもしれませんねというのが、この話のオチ。
「私たちが結婚すれば、あなたの頭脳と私の肉体を併せ持った子供が生まれるわ。」と肉感美女に迫られた劇作家バーナード・ショウが、「あなたの知性と私の肉体を併せ持った子が生まれたらどうします?」と言って断った有名なエピソードとそっくりである。
さて、この文章を読んでいる貴方は、どんなカップルなのでしょうか。
え、独り者だって?
では、なおさら、この話を参考にして下さい。
もちろん、うちは「美男美女カップル」ですが、何か?(笑)
|
 |
お願い
この日記には教育についてのコメントが出てきます。時に辛口のことも多いのですが、これは、あくまでも個人的な感想であり、よりよい教育への提言でもあります。守秘義務や中傷にならないよう配慮しているつもりです。 もし、問題になりそうな部分がありましたら、メールにてお知らせください。
感想をお寄せください。この「ものぐさ」のフォームは、コメントやトラックバックがあるブログ形式を採っておりません。ご面倒でも、左の運営者紹介BOXにあるアドレスを利用下さい。
 (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8) (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)
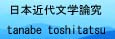
|

 らぬ「ものぐさ」です。
らぬ「ものぐさ」です。 ゼント品。一生ものということで、大枚はたいて買ったR社のブランド腕時計である。買ってたった二か月で、落下させ、ガラスが割れてムーブメントも動かなくなった。かなりの重傷で、一ヶ月以上入院加療の上、先日戻ってきた。もしかしたら香港あたりへ海外旅行していたのかもしれない。修理代は国産高級時計が買えてしまうくらいであった。
ゼント品。一生ものということで、大枚はたいて買ったR社のブランド腕時計である。買ってたった二か月で、落下させ、ガラスが割れてムーブメントも動かなくなった。かなりの重傷で、一ヶ月以上入院加療の上、先日戻ってきた。もしかしたら香港あたりへ海外旅行していたのかもしれない。修理代は国産高級時計が買えてしまうくらいであった。
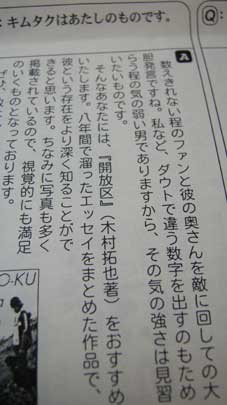

 先の日曜日、金沢二十一世紀美術館に行き、上記の美術展を鑑賞した。早いもので、秋に美術館巡りの日々を送ってから四か月たつ。
先の日曜日、金沢二十一世紀美術館に行き、上記の美術展を鑑賞した。早いもので、秋に美術館巡りの日々を送ってから四か月たつ。 ったので、慌てて行ったのである。
ったので、慌てて行ったのである。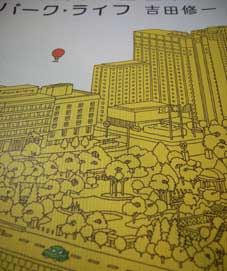 平成十四年、芥川賞を受賞した吉田修一『パークライフ』(文藝春秋社)は、日比谷公園を舞台にした公園小説(?)で、近くのスターバックスが重要な舞台となっている。ああしたお洒落で優しくて、でも、どことなくクールな都会生活のスタイルに、今のシアトル系コーヒー店はよく似合う。ある意味、シアトルコーヒー文化を表徴したスタバ小説(!)という言い方もできるのではないか。この作品は、そうした風俗をつなぎ止めた小説として、後世、名が残るかもしれない。これを、中上健次が、一九六〇年代後半、新宿の「ジャズビレッジ」に通い詰めたあの濃密な関係と較べるとその違いがよくわかる。
平成十四年、芥川賞を受賞した吉田修一『パークライフ』(文藝春秋社)は、日比谷公園を舞台にした公園小説(?)で、近くのスターバックスが重要な舞台となっている。ああしたお洒落で優しくて、でも、どことなくクールな都会生活のスタイルに、今のシアトル系コーヒー店はよく似合う。ある意味、シアトルコーヒー文化を表徴したスタバ小説(!)という言い方もできるのではないか。この作品は、そうした風俗をつなぎ止めた小説として、後世、名が残るかもしれない。これを、中上健次が、一九六〇年代後半、新宿の「ジャズビレッジ」に通い詰めたあの濃密な関係と較べるとその違いがよくわかる。
 荷風の従兄弟、杵屋五叟の次男で、荷風の養子となった人による回想記。去年の六月の刊行。子供の頃、従兄弟二人の間で養子縁組が決まっていたが、仲違いなどで、廃嫡問題がおこるなど、決して順調ではなかった立場の人である。荷風と一緒に暮らした期間もきわめて短い。
荷風の従兄弟、杵屋五叟の次男で、荷風の養子となった人による回想記。去年の六月の刊行。子供の頃、従兄弟二人の間で養子縁組が決まっていたが、仲違いなどで、廃嫡問題がおこるなど、決して順調ではなかった立場の人である。荷風と一緒に暮らした期間もきわめて短い。 (今日はバレンタイン)
(今日はバレンタイン) 今日から、イタリアトリノでの冬季オリンピックが始まった。こちら時間早朝の開会式をテレビでながら鑑賞。向こうは夜である。オリンピックは、本当に人生のお楽しみである。夏冬交互に二年に一度、もうどれがどの五輪だか記憶はごちゃごちゃだが、ニッポン頑張れで、スポーツに別段関心のない私のようなものでも、テレビを観るのが楽しみになる。
今日から、イタリアトリノでの冬季オリンピックが始まった。こちら時間早朝の開会式をテレビでながら鑑賞。向こうは夜である。オリンピックは、本当に人生のお楽しみである。夏冬交互に二年に一度、もうどれがどの五輪だか記憶はごちゃごちゃだが、ニッポン頑張れで、スポーツに別段関心のない私のようなものでも、テレビを観るのが楽しみになる。
 てとれる。実際、私も、数年前出来た車で十分ほどのそんな店によく行く。ヘルシーを心がけて皿をとると、外食だと思われないほどお腹にやさしい献立が出来上がる。煮魚、煮物、菜っぱのおひたし……。
てとれる。実際、私も、数年前出来た車で十分ほどのそんな店によく行く。ヘルシーを心がけて皿をとると、外食だと思われないほどお腹にやさしい献立が出来上がる。煮魚、煮物、菜っぱのおひたし……。 した。最初、どこかで観たことがあると思い、じわっと記憶の底から湧いてくる感覚に心揺れるものを感じた。あのころと、全然、変わっていない。店の名前、何処にあるか、どんな由緒があるのか、今ごろになって詳細を知ることとなる。若い頃は、連れて行ってもらったこともあり、へえ、古いお店だねえ程度で終わっていた。金沢では、泥鰌(とじょう)を蒲焼きにして串で食べる習慣があり、珍しい食べ物と思わなかったせいもある。やはり、東京では超有名な老舗で、当時、我々のような地方出身の若造に、江戸情緒を味わわせたいと、先輩方がわざわざこの店を選んでくださったということがわかる。
した。最初、どこかで観たことがあると思い、じわっと記憶の底から湧いてくる感覚に心揺れるものを感じた。あのころと、全然、変わっていない。店の名前、何処にあるか、どんな由緒があるのか、今ごろになって詳細を知ることとなる。若い頃は、連れて行ってもらったこともあり、へえ、古いお店だねえ程度で終わっていた。金沢では、泥鰌(とじょう)を蒲焼きにして串で食べる習慣があり、珍しい食べ物と思わなかったせいもある。やはり、東京では超有名な老舗で、当時、我々のような地方出身の若造に、江戸情緒を味わわせたいと、先輩方がわざわざこの店を選んでくださったということがわかる。 私は大酒飲みではないと断っておいて……、お酒の話をします。(笑)
私は大酒飲みではないと断っておいて……、お酒の話をします。(笑)
 (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)
(マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)