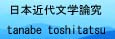|
���̂����@�k�R�Ȃ�܂܂ɓ��X�̒f�z��Ԃ�w�k�R���x�� ��ʁu���̂����v�ł��B ��ʁu���̂����v�ł��B
�@���e�́A���w�E���t�E�Ǐ��E�W���Y�E����E����E�J�����ʐ^�E�|���ȂǁB��T�ԂɂQ����x�̍X�V�y�[�X�ł����A�x���ɏ��������̂�����U�炵�ăA�b�v���Ă���̂ŁA�I���E�^�C���ł͂���܂���B�ȑO�̓��L�ɍs���ɂ́A����́��O�����̕������N���b�N���ĉ������B
�E�w�o�I���ɔ����A���̓����̍X�V���ł��Ȃ��Ȃ�܂����B���̓����̕����́A�ʂ̃u���O�Ɉړ����܂��B�A�h���X�͉��L�ł��B
�G�L�T�C�g�u���O�@�u������a���ʁ`���̂����`�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://hiyorigeta.exblog.jp/
|
�@���k���������ċ����w�ɏo�����A���j�w�̓��c�딎�搶�̍u�`�����B�肵�āu���͗l�̐��E�j�v�B���Ƃ́A���̊G���̎M�A���Ƃɂ���܂��Ƃ���������������n�܂����B
�@��q�C����̓����𗬂̌��ʁA���m�ɒ���������s�����B�����������ŁA������ɂ�������ߗ����ꂪ�L���ɂȂ����B
�@����́A�u�T���ȉƂ̖����g�p�l�Ɨ��ɗ����A�e�̌��߂��������肩�瓦��ċ삯�����������̂́A�������čŌ�ɂ͓�l�Ƃ����ɁA��H�̔��Ɏp��ς���v�Ƃ������́B
�@���̕���́A������̊G���u���͗l�i�E�B���[�p�^�[���j�v�ɂȂ�A��Ԃ̃f�U�C���ƂȂ��āA�C�M���X�̐H�������悤�ɂȂ����B�����̉p���l�́A�q���̍����猩���ꂽ���̕��l�ɂ���Ē����̃C���[�W�����������������ŁA���̎���A�����͐a�m�̍��Ƃ��đ��h���ׂ����Ƃ����C���[�W�������Ƃ����B
�@��A�̊��ɍ����X���āA���{�������푈�ŗ�����D�悷��ƁA���̗L���ȃf�U�C�����g���ĕ��h�G�����ꂽ�B���̐}�������W���Ō���ƁA�{���Ȃ�삯�������ċ���n���Ă���l�����A�����������������o�����{�l�ɒu��������Ă���B���ɂ��A�̍������A�┵�̉H�Ȃǂɂ��ꂼ���x���G�̂悤�ɐD�荞�܂�Ă��āA�����̐��E��S�̂������Ă��邱�Ƃ�����B
�@���́u���͗l�v�̎M�́A���������탁�[�J�[�A�~���g���ЂȂǂ�����āA�����e���܂�Ă������A���͂��̒n�ł͍���Ă��炸�A���̓��{�A�n���̗D�NJ�ƃj�b�R�[�Ёi���u���{�d������i���j�j������Ă���B�F����̂���ɂ��̐}���̎M������̂ł͂Ȃ��ł����Ɛq�˂��̂͂����������R�ł��Ɩ`���ɖ߂��Ęb�͏I������B
�@�M�̊G�Ƃ�����̓I�Ȃ��̂Ɨ��j�Ƃ������ۓI�Ȃ��́A���m�j�Ɠ��m�j�A�ߋ��ƌ��݂��������ƌ������āA��w�̍u�`�炵���X�������O�Șb���Ɗ��S���A�傢�Ɏh�������B����́A���b�����ł͂Ȃ��āA�e���r�ǂ����肪�ٕ����ڐG�̕���Ƃ��āA�ӂ�ɉf�����g���ăh�L�������^���[�ԑg�ɂł����Ă����Ɩʔ�����������Ȃ��B
���͔M�S�Ƀ������Ƃ����̂����A���āA���k����͂ƌ���A�قƂ�ǕM�����Ă��Ȃ��B�u�����Ă͂�����B�v�Ƃ���������B�ǂ����A���ꂪ�����Ƃ����ӎ����N���Ȃ������悤���B
�@�m���ɁA�ނ��N�������Ǝv���Ă�����̂͒����I�ŒP�ꂾ�B���j�͌Ñォ�猻��^�������B�Õ��͌Õ��A���㕶�͌��㕶�ŕʁB�p��ƍ���A��w�Ƃ��Ėڎw���Ă���Ƃ���͓����Ȃ�Ċ��o�͂قƂ�ǂȂ����낤�B�����͈͂����ԗ��ĂĐi�ނ�������ׂ����Ƃ������Ƃ�����B�搶�����Ɏ����������珑���B����ȃ��x���ł���B������A����̂悤�ɍ�����؎g�킸�A���A�L�͂ɒm�������т���悤�Șb���y���ނɂ́A�܂��A������Ɗ�{�ƂȂ�u��b�w�́v�Ɓu�w�K����P���v������Ă��Ȃ��B���ꂪ�A���̎����̎O�N����������A���̂�����̂��Ƃ̓N���A����Ă��邩��A�傢�Ɋy�����Ƃ��낤�B�䂪�Ζ��Z�́A�ŏ㋉���̃��f�B�l�X�́A�o�b�`���ł���i�ƐM�������j�B
�ŋ߂́A���������u��w���w�v�����B�V�z�Ȃ�������̎��R�Ȋw�������͏��߂Č������A���������̃G���g�����X�Ȃ��ґ�ȋ�ԗ��p�̐v�ŁA�z�e���̂悤�ȑ���ɋ������B
�@���̊��A��R�S�čZ�n�Ƃ����b�܂ꂽ������i�Ɨ��s���@�l�j�̊��������āA�܂��A���k�l�ɁA������w�����Ă݂悤���ȂƎv���đՂ����Ƃ����A���肪���`������I�z���̍s���͂����s���ł���B  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
|
 |
|
�@��T�A�g���̗x��̃X�e�[�W���������̂ŁA�V���Ƌ�������N����كz�[���ɏo�������B���̌�A�߂��̌����̃x���`�ň�x�݁B�H�̓����܂�̒��A�O�̋�C���z���͖̂{���ɋC�������悩�����B
�@���낻���`�������悤�Ƃ������ɂȂ��āA�����A�ǂ����ł����ɂ��悤�ƌ����o�����B
�@���������A�����������悤�ɂȂ��āA�p���ȊO�͂��܂�o�����Ȃ��Ȃ������ɂƂ��āA���ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��܂܊O�ɏo�Ă���Ƃ����̂͋M�d�Ȏ��ԂȂ̂��낤�B�����A����D���̔ނ́A����Ȏ��ԁA�u�O�ł����v�������������̂ł���B
�����ŁA��قɖ߂�A���r�[�̃��E���W������𒍕����āA�G�k�𑱂����B�@���܂łƓ�������������B���ꂪ�ł��邱�Ƃ̉x�т͉����̂ɂ��ウ��B���̋C�����͂悭�������B
���Ⴍ���Ⴈ�݂��D���Ȃ��Ƃ������U�炩���Ď����߂����B�����A�l�̂��Ƃ͌����Ȃ��A�����v���Ԃ�́u�O�ł����v���Ȃ��Ǝv���Ȃ���c�c�B
|
 |
|
 �u���Ƃ����v�Łu�Ƃ�Ƃ߂̖����b�v���ƈ��삳�����Ă���悤�ɁA�F�l���m�A�H�������ɂ��Ȃ���̎G�k�Ƃ����������ŁA��������������������A�y�������������B �u���Ƃ����v�Łu�Ƃ�Ƃ߂̖����b�v���ƈ��삳�����Ă���悤�ɁA�F�l���m�A�H�������ɂ��Ȃ���̎G�k�Ƃ����������ŁA��������������������A�y�������������B
�@���̐́A��������A�g�s�~�V����肪�悭�Ւk�W���o���Ă��āA�y�����ǂ��̂��B���̖{�́A���̍��̖{�̓���������B�k����́u��O�̐V�l�v����ɐ��ɏo�����A�ꎞ���A�}���{�E�E�ϒK���Ńu�[���ɂȂ��āA�F�B�̗F�B�݂����ȊW�Œ��ǂ��Ȃ����B�����A�g�s�Ȃ����A���삳��ɂƂ��Ėk����́A�����Ȃ��Ȃ����厖�ȓ��Ƃ̗F�l�ł���B
�@�S�Z��̑Βk�́A�����N���Ȃ���A�������������ɂ��đ������ɂ����ƒQ���k����A�����Ɗ撣��Ɨ�܂����삳��Ƃ����W�Ői�ށB
�@��b�̒[�X�ɖg�̉̂������o���͈̂��삳��̂ق��B�������������h����̐l�̑��q�ŁA�ǂ��ƂȂ��m�[�u���ȕ��͋C�����k����ɁA�u�ԓ���������ٖ̈��������삳������܂�{�������Ƃ͂Ȃ��炵���B���̉�b�ł��A�k����́A���\�A�`�N���Ƃ������Ƃ������Ă��邪�A���݂ɂȂ��Ă��Ȃ����A���삳��������Ă���B�k����͈��삳����u��y�v�ƌĂт����Ă���̂ŁA����l�A�C�̒u���Ȃ���y�E��y�̊ԕ��Ȃ̂��낤�B
�@���܂�̏�蕨���Ԃ�Ɉ��삳��́u�ϐl�v���Ǝv���Ă���k����ɁA�M���Ɍ����Ă͐S�O�ƈ��삳�����Ƃ�����������A�ǂ�ł��Ėʔ��������B
�@�Ō�̑Βk�͕����\��N�̂��́B���ꂩ��Z�N�����B���삳��͍��N���\�Z�B�F����̂悤�ɋ�\�܍��炢�ɂȂ��āu���A���ȂȂ��悤�ȋC������v�ƚ����Ă�낤�ƌv�撆���Ƃ��B
�@�V���Ђ̃T�C�g�ɁA���썲�a�q�A�֓��R���A����l�̖�����ɂ�镃�e�̍s��\�I�Βk���ڂ��Ă���i�u�{�镃�A�������A�Q�����v�i�u�g�v��Z�Z��N���̍Čf�j�j�B�ǂ������}�V�ȕ��e���Ƃ����̂��b�̃e�[�}�ŁA�����Ɍ����ƁA������̗��b�̂ق�����R�ʔ����B���썲�a�q����́A���╃�e���L���l�����A�����t�^�Ƃ��Ă�����ڂ������D�̃I�`�ɂȂ��āA�����Ɣ��ꂽ�̂ł͂Ȃ����ȁB
�i�NjL�j�u��O�̐V�l�v�̂���l�A�����M�v�������S���Ȃ����B��\��B�Q�ĂāA�������̕��̔N��ׂ��B�����͑��Y�A���\�Z�B���쏁�O�A���\�܍B���A��O�̐V�l�����d�Œ��V����B���a�O�\�N��͉����̂ł���B
|
 |
|
 �\�N���炢�O�ɎB���������ʐ^�ɊȒP�ȃG�b�Z�C�����B���X�F�Ă�����̂���Ȃ��ōڂ��Ă���̂̓m�X�^���W�[�̉��o�ł��낤�B���ۂ̉����Ɍ��肵�����̂ł͂Ȃ��Ƃ����Ƃ��낪�~�\�ŁA�R�̎�̎ʐ^��������B�����Ƃ����C���[�W�ō\�������u�܂ڂ낵�̒��v�Ƃ����R���Z�v�g�ł���B�������݂ȕ��i�����邵�A������Ď��݂��Ȃ����̂�����Ƃ����B �\�N���炢�O�ɎB���������ʐ^�ɊȒP�ȃG�b�Z�C�����B���X�F�Ă�����̂���Ȃ��ōڂ��Ă���̂̓m�X�^���W�[�̉��o�ł��낤�B���ۂ̉����Ɍ��肵�����̂ł͂Ȃ��Ƃ����Ƃ��낪�~�\�ŁA�R�̎�̎ʐ^��������B�����Ƃ����C���[�W�ō\�������u�܂ڂ낵�̒��v�Ƃ����R���Z�v�g�ł���B�������݂ȕ��i�����邵�A������Ď��݂��Ȃ����̂�����Ƃ����B
�@�ʉَq���A�K���̔ԑ�c�c�B���̎q���̍��A��������ł�������O�ɂ��������i�ł���B�������Ⴂ���A����Ȏʐ^���B���Ă����悩�����ȂƎv���Ȃ���ł��߂���B�Ȃɂ����Z���ォ��̃J�������m�ł���B�ʗ������͎O�\�N����B
�@���ɁA����ɂȂ��������i������B���������͉͌��̒�������A�傫�Ȑ�̂قƂ�̎ʐ^�������邪�A���������i�F�͂�����ɂ͂Ȃ��B�����ɏZ��ł����̂ŁA���i�Ƃ��Ă͌������Ƃ͂��邪�A�����Ƃ��Ă�����̋C�����͓����Ȃ��B���Ƃ��ƁA����͑O�c�l�̌�鉺�A�����I�ȈӖ��ł̉����炵�������͂Ȃ������B
�@���ňꖇ�A�Â��K���́A�E�ߏꂩ�����B���Ă���ʐ^�ɖڂ��Ƃ܂����B�l�����I�O�A���������ʂ��Ă����ڍ���߂��̑K���̒E�ߏ�Ƃ�������ʼn������������B���̎��A���C����オ���đ̂��܂��ԁA�ؑ���̒E�ߔ��̉��Ɉ֎q��u���āA�������Ȃ������̂����߂Ăڂ��肵�Ă��邢��̂�����̊y���݂������B
�@�����A�����̑K���́A�܂��A�R�����肰�Ȍ�a���肪�����c���Ă��āA�����̐����̒��ŁA�Â��ǂ������������ł��g�߂Ɏ����ł����Ԃ������B�]�˂̖��c��ɐG��Ă���A����Ȋ��o�����̎������Ă����悤�Ɏv���B
�@���̑K���́A���ւ����j���i����͂Ӂj�̉����A�E�ߏ�͍��V��Ƃ����ґ�ȑ���ŁA�吳����Ƀu�[���������āA�����Ă��������l���̌����ɂȂ����̂��Ƃ������Ƃ��A��Ɍ��z�̖{�Œm�����B���̔R���Ɍ��z�p�ނ��g���Ă��āA���ɎR�ς݂ɂ��Ă������B�����Ă��đK�����߂Â��ƁA�̔R������������������Y���Ă������Ƃ����ł��悭�o���Ă���B�V�����ƌo�c��ŁA�����̌Â��K�����������Ă���Ƃ����j���[�X�������Ƃ�����̂ŁA�����A���̌����͂Ȃ����낤�B
�@����ł̗c���̋L���Ɛ̂̓����ł̋L���B����́A���đ̌��������Ƃ��������Ăі߂���Ƃ��B����ɁA�̌��������Ƃ��Ȃ����������̐�����z�����ăC���[�W�����Ƃ������B�u�L���v�Ɓu�z���v�́A�悭���Ă��邯��ǁA�ǂ����Ⴄ�B�L���͔]�̉��̕����璊�l���J����悤�ɁA�z���͔]�̕\�ʂ���N���Ă���悤�Ȋ����ŏœ_�����ԁB������J��Ԃ����B����́A���̎ʐ^�Ƃ��܂ڂ낵�̒����o�����悤�ɁA�����L���Ƒz���𗊂�ɁA�������̂܂ڂ낵�̒������o����Ƃł��������B
�@�r���ɓ���G�b�Z�C�́A�m�X�^���W�[���������Ă鑕�u�݂����Ȃ��́A�����������̂ł͂Ȃ��B�����ݏZ�҂ɂ́A�����́A���I�����K�C�h����̓I�Ŋ������낤�B
|
 |
�@���x�����̓��L�ŏЉ�Ă���l������N�̑�O���W�w���j�Ձx���ԋL�O����s�����w�܂���܂����B�����A�������\����āA��̃��[�J���j���[�X�ŗ��ꂽ�������B�����ɒm�l����A�ޕ����Љ�������Ă����l�ł͂Ȃ����Ɠd�b������A���܂����A�����A���\�������ƋC�Â����B���A���ɒx���ŁA�ނ̐���p�������˂Ă��܂����B
�@���ځA�ނɐq�˂��킯�ł͂Ȃ����A���a�����Ƃ�������ȂǂȂ��A����̎��W�Ƃ��Ăǂ��]������Ă���̂��C�ɂȂ��Ă����Ǝv���̂ŁA���̎�܂͖{���ɂ��ꂵ�����낤�B�a�������邢��C�ɕ�܂�Ă���̂ł͂Ȃ����B������\�N�Ő��x��������Ă��Ȃ��Ȃ܂���O�쉞���c�����ǁA��͂�������B
�@���ꂩ��A�܂��܂�����ɒe�݂������낤�ƁA�v���Ԃ�ɔނ̃u���O��`���Ă݂�ƁA��������{�s���ꂽ�u��Q�Ҏ����x���@�v�̂����ŁA�x�����z���������~����~�߂��Ɍ��z����A���̎��W�o�ł̂��߂̎����ςݗ��Ă��o���Ȃ��Ȃ�̂ł͂ƐS�z���Ă��镶�͂��ڂɓ������B
�@�H��Ȃǐ�����̂ɕK�v�ȕۏႵ�����Ȃ��A���Ƃ́u����������v�Ȃǂ͎��ȕ��S�łƂ������{�̍l�����炵�����A���ڎ����̕��r���Ȃ��̂�����A���ǁA�s�����͉Ƒ��̕��S�ɂȂ�B�e���ɉ҂��̂���Ƃ���Ȃ炢�����A�N����炵�̂悤�Ȃ���́A����҂̎�v�ҕ��S�������Ȃ��Ă��邵�A�����s���Ȃ��Ȃ�ƒ���o�Ă��������B���ׂĂ݂�ƁA�u���E�x���@�v�ȂǂƂ����A����������Ă����炵���B�܂��������s���ł������B
�@���̒��A�����Ȃ���肾���A�t�����̂Ƃ������A��������̃A���e�i��t�L���Ă����Ăق����B
�@���ꂩ�瑽�Z�ɂȂ�̂�������ƐS�z�B���������u�y�����v�����Ă��������B���߂āA���̂��т̎�܁A���߂łƂ�������܂��B
|
 |
|
��T�A�w���ɏo���������łɁA�V�������������������ɏo�������V���b�s���O�{�݂ɗ���������B���X���������ɕ��сA�C�ɓ������X�ɓ���y�������`�̃A�E�g���b�g���[����A�z���鉡���̌����B�V�F�[�h������Ƃ͂����A���������O�̒ʘH������Ȃ���ἨׂX�ɍs���Ȃ��\���ɁA�v�w�Ƃ��ǂ��A����̖k�������ł͂Ȃ��ˁA�~�͗��Ȃ��Ȃƕ]���͒Ⴉ�����B
�@���̎��A�אڂ̕x�R���{�̑�^���X�ɂ��������B���������������ԎG�ݓX�����݂��Ă��āA�J�E���^�[�ɒu���Ă������Ǝ��ɏo���Ă���~�j�R�~�������������B�^�[�Q�b�g�͖��炩�ł���B
�@�Ȃ�ł������ő�̔����ʐς������ŁA���R�Ə��������сA���I�ɂ͂킴�킴�ԍ����U���Ă����āA���ړ��Ă̖{�ɍs�������₷���̂��E���̂悤���B�܂�A������Ɛ}���ق̕ˎ����ɂɐ��荞���悤�ȉ��o�����Ă���B
���������A���N�A�Ґ썶�݂ɂł����֓����{�̓X�́A�킴�킴�i���������菑�I�̍������Ⴆ���肵�āu�{�̐X�v���U�邩�̂悤�ȉ��o���Ȃ���Ă����B
�@����Ɋr�ׁA����s�����ɉ؊X�ɂ���n�����{�̘V���X�́A�͗l�ւ��������̂͂������A�悭������������ƁA���������A�����Ȃǂ��ł�����{������Ƃ����������ɂȂ����B
�@����͌��O���{�ɋ���Ēn�����{���ޏk���Ă���ƌ����ċv�������A���Д̔�����O�ł͂Ȃ��������B
�@���̕x�R���{�̓X�ŁA�u��i�G�C�j���Ɂv�Ȃ�V���[�Y�̓��W�����Ă����B��ɓ����������ɂ������ŁA�J�e�S���[�́A�o�C�N�A�ނ�A�J�����A�ʐ^�ȂǁB�����������ɂ����邱�Ƃ����m��Ȃ������B�ʔ������Ȃ̂ŁA���̒��������������ƂɌ��߁A�}�j�A�b�N�ȃJ�����]�~�{�͔����āA�ʐ^�{��I�B�����ɖO������p���p���߂��낤�B
�@���������{�Ƃ̏o��́A�͂��߂čs�����{������Ȃ�ł͂̊y���݂ł���B

|
 |
�@�����̌ߌ�A����ĉJ���~��܂ŁA��T�ԁA�D�V���������B
�@�E��̊�����O���ςĂ�����A�O�͂ɔw���A���������{�Ԃ����Ă����B�ŏ��Ɍ������̂͐�T���̂��ƁB�������̂̊O����ŁA�ꎞ�̓A�����M�[�̍��{�����̂悤�Ɍ���ꂽ����������B�����͂������A�ǂ�����Ƃ��Ȃ�����Ă��č���B
�@������A�J�ʔ��N�̎R���H��ʂ�����A�������̂�����Ƃ���ɑp�����Ă��ċ������B��������E��֔��ł����̂��낤�B���̉��F�̉ԂŏH�̐����m�邱�ƂɂȂ�Ȃ�āA������ƁA�����Ƃ����v���������B
�@���̓��A�����b�ɂȂ��Ă��鎩���Ԑ����X�̏H�P����ω�ɏo�|�����B
�@���������ϕ��o��Ղ��Ă���A�W�����Ă������V�Ԃɍ����Ă݂�B�����Ȃ��̂ŁA�����V�[�g�ɍ����Ă����Ȃ��Ȃ��āA�����̂Ƃ���A�Ԃɋ����������Ă����B���ߏ��������Ȃ��̂�����A�ǂ��ł������Ƃ����������ł������B
�@�V�Ԃ̓���������B�����������A���̎Ԃƌi�F������Ă݂���B�}�ɁA������ƐV�ԂŃh���C�u���������̂��Ƃ����C�������N���Ă���B�����Ȃ�A�҂đ҂ĂƎv���̂�����ǁA�ł��A����ȗ~���o�Ă���̂͂������Ƃ����m��Ȃ��B���L�̎Ԃ��A�����\�O�N�ځB�V�ԂŒ������h���C�u��ڕW�ɁA���̍��̏��q������L���ӗ~�Â��ɂ���Ƃ����̂������A�C�f�B�A���B���������蔃���ւ��邱�Ƃ͂��Ȃ����肾���A����ȏH�̗D�����������ɗU��ꂽ���̂悤�ȋC�����ɂȂ����B
�@����E��ł������H�b��B
�@�u���̋G�߁A�ȑO�́A�悭�d���A��ɑ�掛�Ɋ���Ă��Q�肵�����̂ł��B�[���̏H�̋�C�ɕ�܂�Ă��邨�����U�A��O�������̒����݂��Ղ���̂��������̂ł���B�v�Ɠ����̏����Ɍ������A�u�����悭���̏�ɂ���ь牀�ɍs���āA�������Ă̗ь���܂��B�������̂�������z������ł����ǂˁB�v�ƕԂ��ꂽ�B
�@���R�ɓo��Ƃ����_�ł͓��������ǁA���_�͂����ԈႤ��Ȃ��ł��傤���ƁA���͓˂�����ŁA�������͂�����Ƃ������ɕ�܂ꂽ�B
�@�߂����₷���[���A����ȓ��́A�d���A��ɉ�������������̂��߂Ɋ�蓹���������Ȃ�B�ł��A�H�̗z�͒ޕr���Ƃ��B�������ƈÂ��Ȃ��Ă��܂��āA�����ɉƗ������Ȃ��Ă��܂��B
�@�H�̗[�܂���́A��X�ɃA���r�o�����c�Ȋ�����^��ł���悤�ł���B

|
 |
|
�@�R�萳�a�ɒm�I�Љ�̍\���͂������͂�����i�u���{�����ƌl��`�v�j�B���̒�ԋ��ނł���B����ɂ��ƁA�������́A�G���[�g�Ƒ�O�Ƃ����P����ɍ\���������̂��A�吳���A�G���[�g�w���ʓI�Ɋg�債�A�����ȃG���[�g�ƒm�I�Ȓ��ԊK�w�ɕ��������Ƃ����B�ނ́A������u��g���ɂ�����l�ԂƂ����ǂސl�ԁv�Ƃ�������₷��栂��Ő������Ă���B
�@��������A��w�i�w���͌\�p�[�Z���g�����B��w�Ő�勳������҂��C���e���Ɖ��肷��ƁA����́A�l���̉ߔ������C���e���Ƃ������\�L�̖c����ԂƂȂ����Ƃ�����B���̌��ʁA�����̐��̘_�����ǂ݂��Ȃ����A������̈����ʂ��ő�w���o���悤�ȃ��x���̎҂��吨������悤�ɂȂ����B�R�藬�Ɍ����ƁA�u��g���ɂ���ɂƂ邱�Ƃ������Ȃ��C���e���v�̒a���ł���B
�@����ł����i�͂Ƃ����B���̒��A�d�����ו��������悤�ɂȂ�������A�ɏ��͈͂̒m���ł��A�����Ǝd���͂��Ȃ��邵�A�����͐�勳��������Ƃ��ƐM���ċ^��Ȃ��B��������̃C���e���̕S�ȑS���I���{���x�����炷��ƁA�m���ʂ����{�I�ɕs�����Ă���ɂ�������炸�A�ӎ��̏�ł́A�u���Ȃ��Ƃ��I���͔n���ł͂Ȃ��͂����B�v�Ǝ��ȓ��肷��Ɏ������B
�@���̓I�m�I���x������������Ɋr�ׂ����Əオ���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����A���̎��セ�̎���ł̃C���e���w�́A�{���I��`�I�ɏ����̂܂܂̂͂��ł���B�܂�A�}�������̂́A�C���e���Ǝ��ȔF�����Ă����O�w�Ȃ̂ł���B
�@���{��`�̎���A�^�̃C���e���̓C���e���ł��邱�Ƃ��ւ�Ȃ��Ă��悩�����B�������ɃC���e���Ȃ̂�����A���肪���������Ă��ꂽ�B�������A���̎���C���e������A�N���������h���Ă�����Ȃ��B�����ŁA�����Ŏ���ɒm�炵�߂�K�v������B�܂�́A���Ѝs���̕K�v�����o�Ă����킯�ŁA���ꂪ�A���l�̎��̌����ƂȂ��Č���邱�ƂɂȂ����Ƃ������ƂȂ̂��낤�B
�@�́A�����͊w���Ȃ��ł�����Ƃ������̒Ⴂ�l���吨�����悤�Ɏv�����A���ł́A�������������Ȑl��������͍̂���B
�@���̈�����f����ɂ͂ǂ�����������B
�@�܂��A���O�̒m���ł��ǂ�ǂ�z������̂��C���e���Ƃ����ӎ�����Ă�Ƃ悢��������Ȃ��B���̒��A�m��Ȃ����Ƃ��炯���Ƃ������ƂɋC�Â��Ύ��Ȗ����I�L�\���͒ቺ����B
�@�����āA�������A�v���オ�炸�A�u�����ɐ����悤�v�Ǝ��o����S����Ă�Ƃ������Ƃ����C�悭���邵�������̓��͂Ȃ��悤�Ɏv���B�m�I���x���͈�w�̌��オ�K�v�����A�����Ă����̂ɍŒ���K�v�������������Ė��Ȃ������B�������A����Ƃ͊W�Ȃ��u����قǓ��𐂂���䂩�ȁv���_�̟��{���s�����B�×����猾���Ă���u����m��v�u�����킫�܂���v�Ƃ������ƁA�����A������m�邱�ƁB����́A�Ƃ���Ȃ������A����d����C�����̌���ɂȂ�B
�@�����炭�A�q�������͐�������s���Ȃ̂ł͂Ȃ��A���ꂪ�s���ȑԓx�ɂȂ邱�Ƃ�m��Ȃ������ł���B�s��������u�����̔O�����Ƃ��v�ł͗����ɂ������Ȃ��Ă��Ȃ��̂��Ƃ͏d�X���m���Ă��邪�A��������t���S�ʂɉ������ĂČp�����M���Ă������Ƃ̌��ʂ͏��Ȃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Ȃ��Â߂��������_�����A���_�̎����悤�̋���́A�̂̂ق�����قǂ������肵�Ă����B���N��NHK��̓h���}�u�������ҁv���ςĂ���ƁA���m�i���̂̂Ӂj�̓��Ƃ��āA�ǂ����̋ǖʂ�I�����A�����Ă������Ǝ��₷���ʂ��悭����i�A���A�R����L�͉�����̈ӌ��ɖӖړI�ɏ]�����ǁi�j�j�B�Ȃ̕���m������ŁA���z�̃g�b�v�ɁA����ׂ��u���z���v�������Ă���l�́A�z�Ƃ��Ĕ������B
�@�u�����͂ǂ�قǂ̐l�ԂȂ́H�v
�@�u�ǂ�Ȑl�ԂɂȂ肽���́H�v
�@�܂��A��������l�������A�������o�����������A�͂�����u������ڕW�v�ɂ�����ӎ��Â������d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B���k�����t���Z�����Ċ̐S�Ȃ��Ƃ����Y��Ă���B
�@����A�d���̘b�Ɨ��ނ̂ŁA�C�����������āA��Ȃ��炦�炭�����L���Ȃ����悤�ȁc�c�B
�@���������A�����̂Ƃ���A�S�R�A��g���ɓǂ�ł��Ȃ��c�c�B
|
 |
|
�@���͋����[���ǂ̂����A��ŁA�l�b�g�̔��u�A�}�]���v�̓ǎ҃��r���[�����ċ������B�O���̈�ȏオ���]�ł���B���ꂽ�ƒf�E�ϑz�ŁA����Ȑ搶�ɏK�����q���͉��z���A���͂��̐搶���u�������܂��v�Ƃ����̂����������B����Ƃ��Č��������̂��A���̏͂Ŏ����Ƃ��Ę_���Ă���Ƃ��A�L���{��_�Ɏg���Čy�����Ƃ��A�ꉞ�A�ᔻ�Ƃ��Đ������闝�R�������Ă��邪�A���̍������ɂ́A�Ⴂ���������̐搶�͔n�����Ă���Ƃ�����Q�ϑz�I�ȕs����������悤�Ɏv�����B
�����������ɘ_���I�Ȃ����炢�̕��͂�����ǂ�ł����ƁA�������U�����ꂽ�Ɗ�������ߏ�ɔ�������Ƃ����A�������ŕ��͂��Ă��錻��̑ΐl�W�̖�肪���̂܂܌`�ƂȂ��ĕ\�o���Ă���悤�Ɋ������B�����A���������ƁA���������M���̑ԓx�����A�܂��Ɏ�҂��������Ă���B�M�������̍�҂Ɠ������������Ƃ������_�������ƕԂ��Ă���͂��ŁA�c�_�͌����Ȃ܂łɐ��|���_�ƂȂ�B
�@���̖��A���r���[�ɔ��_�������悤�ȎႢ��l��������A���̏��w�Z���獂�Z�����炢�Ɍ����Ɍ���Ă���悤�Ɏv���B�u��ҁv�Ƃ��������̂ŁA������Ɣ��R�Ƃ����c�_�ɂȂ�A����͍��̐��̒��S�̂̌X���ł��傤�Ƃ������ƂɂȂ镔��������悤�Ɏv�����B���猻��ŁA�����Ƃ��ċN�����Ă�����Ƃ��āA�Ώۂ����肵�āA�����܂ŋ���S���w�I�ɕ��͂���Ί���_�I�ᔻ�����Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@����ɁA��������ꂸ�Ɍ����A����w�̖{�͋ƊE�n�E�c�[�{�ł���B�Ⴆ�A�c�Ɖ�c�ŁA�ڋq�������ɂ��������Ă��̋C�ɂ����ď��i���킹�邩�ɂ��ĉ�c���Ă����Ƃ��āA���̓��e�̋q����������A�����C�������Ȃ��̂Ƃ悭�����Ƃ��낪����̂ł͂Ȃ����B
�@�{�̍Ō�ɁA���҂͂�����x�������肵���u��������v���ƒ��Ă���i�ꕔ�̃��r���[�A�[�ɂ́A��������ꂽꀂ̐��������z�炵���j�B���̓_���A��X�������m�A�������ɂ��Ă��邱�Ƃł���B�����������ɑS�R����������Ă��Ȃ��q�́A�����̉䂪�Ԃ̐������̗����������B�҂ɂȂ��āA�{���ɏ�Ȃ����Z�����o���オ��B�����āA��Ȃ���l���o���オ��A��Ȃ����{���o���オ��c�c�ƁA�����B�i�Â��j
|
 |
�@���N�قǑO�A�Ǐ������Łu�{��ǂގ��ԁv�Ƃ����̂��������B���鐶�k�����E������Ă����̂Œ��ӂ�����A���̖{�ʔ����Ȃ��Ƃ����B�ȑO�ǂ��Ƃ�����̂��ƕ�������A���A���œǂ����̔��f���Ƃ����B����Ȏ�������͋������Ǝv�����ƕ�������A�������A�ʔ����Ȃ����̂��������邱�Ƃ̕�����قǂ��������Ǝ��M�������Ĕ��_���ꂽ�B
����搶�A�L���ŏ����k�ɒ��ӂ����A�ǂ��̃N���X�̒N�ł����Ɛq�˂���A������������ɖ����ׂ��ł͂Ȃ��ł����ƌ���ꂽ�B������ƐE�����ɗ��Ȃ����Ƃ����ƁA�u������p��������̂ŁA�s������͂���܂���B�v�ƁA���тꂽ�l�q���Ȃ��A�����ς苑�ۂ��ꂽ�Ƃ����B
�@���̎�́A��l���猩��Ƃт����肷��悤�ȁu�s�����v�ɁA�ŋ߁A���������ŏo��悤�ɂȂ����B��萶�k�ł͂Ȃ��A�������ʂ̐��k���݂���̑ԓx������A�Ȃ��������������B�ǂ������̎q���́A�搶��搶�A��l���l�Ǝv���Ă��Ȃ��Ƃ��낪����B��̘L�������ȂǁA���ŏ����ɐ���������ςȃI�W�T���Ɠ������������ꂽ�̂��낤�B
�@�����́A��c�ŁA���̎q���̌�����A���ʑf�s�ʁA�F�X�ȃe�[�}�ŕ��͂���B�����āA���̎q���͂����������������̌X��������ƌ��_�Â��A�ł́A�ǂ����������������l����B�������A��X�͋���w�҂ł͂Ȃ�����A�w��I���v�I�ɔc������킯�ł͂Ȃ��B�����S���̋��ʔF���Ɣ[��������A�����������̂ƍl����B
�@���̖{�̒��҂͋���S���w�̑�w�����B�䂪�Ζ��Z�̉��l���̐搶���ǂ݁A���X�����Ă��邱�Ƃ����͂���Ă��邩��Ɗ��߂Ă����������̂ŁA������ēǂB
�@�m���ɁA�����ɋ����Ă��鎖��̂������́A��X�̎��͂Ŏ��ۂɋN���Ă���B��҂́A���̎�҂̓w�͂��Ȃ��ɂ�������炸�����͗L�\���Ǝv������ł���l�q���u���z�I�L�\���v�Ɩ��t���A���l���������ƂŎ��Ȃ̐��_�̕ۑS���͂����Ă���ƕ��͂���B���Ҍy�����邱�ƂŁA���z�I�L�\���������A���̂��߁A�w�͂��y������̂ŁA�w�͌o�����R�����A���R�A���s���ď����A���̐S�̏��𑼎Ҍy���Ŗ��ߍ��킹�悤�Ƃ���Ƃ������z���N�����Ă���̂��Ƃ����̂ł���B
�@���������A�ŋߖڂɂ���҂̐S���ɒ��Ⴕ�A�V�����x���ł܂Ƃ߂��̂́A���̖{�������炭�ŏ��̕��ނ��낤�B���݁A���\�����̃X�}�b�V���q�b�g�ɂȂ��Ă���B�ߋ��Ƀf�[�^��~�ς��������v�����Ȃǂ�����킯���Ȃ��A�ߋ��Ɣ�r���Ă̕��͂��ł��Â炢������A�ł��邾���������ĂāA�L���Ȗ{�Ȃǂ��Љ�Ȃ����_��i�߂Ă���B�q�����������앶�͍l�������o�Ă��邩�炢�����͎����ɂȂ�͂������A�̂̂��̂͂܂������c���Ă��Ȃ��ƒ��҂͍����Ă��邪�A�܂��������̒ʂ�A����̐搶�́A�N�x���I���Ɛ��k�̏��������͕̂ԋp���p�����Ă��܂��A�茳�Ɉꖇ���c���Ă��Ȃ��̂����ʂł���B�i�Â��j
|
 |
 �u���ԁA�H���A�Ґ��̐��E���y���ށv�i�����U�����c�j�Ƃ������̈�Ƃ��Ď��{���ꂽ�u�O�����f���f��v�̑�����ς�B����A�ꏊ�͋���s�����}���ٓ�K�I�A�V�X�z�[���B�f��́A�����Ґ�����u���ɂ������Ɓv�i��f�j�B���a��\���N�A��������j�ē�i�ł���B�ڂƕ@�̐�ɕ����I�{�݂����邱�Ƃ̗L������������B �u���ԁA�H���A�Ґ��̐��E���y���ށv�i�����U�����c�j�Ƃ������̈�Ƃ��Ď��{���ꂽ�u�O�����f���f��v�̑�����ς�B����A�ꏊ�͋���s�����}���ٓ�K�I�A�V�X�z�[���B�f��́A�����Ґ�����u���ɂ������Ɓv�i��f�j�B���a��\���N�A��������j�ē�i�ł���B�ڂƕ@�̐�ɕ����I�{�݂����邱�Ƃ̗L������������B
��f�ɐ旧���A�}�X�E�搶�ɂ��Ȃɂ��ėv����������B���������A�Ґ��ɂ͌��̂Ȃ���Ȃ��Z�킽���Ƃ̊��������������Ƃ�A����g�p���̎O�\���~�́A�����̎q���������������؋��̌����߂Ɏg�����Ƃ����悤�ȗ��b����I����ċ����[�������B
�@�q���h���g������������̖�����i���}�`�q�j�ɑ��āA���Ԃ����e��ȌZ�i�X��V�j�A�ߏ����Z�J���̗{�q�̒j�Ƃ̌��������܂������Ȃ��������̖�����i�v����q�j�A���̎O�l�̌Z���𒆐S�ɁA�R���N���[�g��݂ɂȂ��ė����Ԃꂽ��t�̕��i�R�{��O�Y�j�ƁA������萷�肵�Đ������������i�Y�ӌH�q�j�̓����ߍx�̕Ƒ��ł̐����𗍂߂Ȃ���`������i�B
�@�s�܂�������̊w���i�D�z�p��j�ɖ��ւ̈�����Z���f�I�����ʂ�A������Ƌ��ɓ����ɖ߂郉�X�g�A����ȌZ�ł�����������Ȃ鎞������̂�ƌ���ʂŁA���̌q�������ғ��m�̏�̐[����\������B���e�ł���̂ɑ����ƈ����������Ƃ����S�̐^�������܂��`���Ă���B
�f��̏�ʂƂ��ē����͈�x���o�Ă��Ȃ����A�s��Z�܂��̖���l�́A���X�̋��ɋA���Ă���B�j����̐������ƂƂ��Ă���o����́A����A�s��̂������̑��ʁA���́u�ޔp���v���ے����Ă��邵�A�Ō�t�Ƃ��č��x���Y�t�̎��i���Ƃ낤�Ɗ撣���Ă��閅����̐����́A������s����ł����ł��Ȃ��u�A�J�f�~�b�N�v�ȑ��ʂ��ے����Ă���B������ɂ��Ă��A���̔_���ɑ��݂��Ȃ��V���������ł���B�ޏ���̋A�ȂƂ́A���Ȃ킿�A�ߑ�̑O�ߑ�ւ̗����Ȃ̂ł���B
�@�n���Ɏc�����Z��V�g�́A���ߏ��l�ɒp�������Ȃ��悤�ɂƂ������z�̋����ȗϗ��ς��\���Ă���B�Z������ɐh��������̂́A�Â��ϗ��Љ�ɐN�����Ă����u�s��v�̂������킵���ɑ��鋑�┽���Ȃ̂ł���A����Ɋ���Ȃ̂́A�c�ɂɌ������Ă���m�I���ʂւ̓��ۂ����邩�炾�낤�B
�@���Ȍ��͂������Ă����ߋ��ƈ���āA����Ԃ�čȂ̉҂��������܂����Ď�������ł���悤�ȕ��́A���͂�A���̏�́u�����v�ł͂��蓾�Ȃ��B���q��V�g�ɂ���͈ڏ����Ă���ƍl����ׂ��ŁA�Z���e�\�Ȃ̂́A��Ƃ𑩂˂悤�ƕ������镃����̌����Ă��邩��ł���B
���������r�Ԃ镃�ł���Z�Ɋr�ׁA��͂����܂ł�����ł���B�ǂ�Ȃɖ���������ɂȂ��Ă��ӖړI�ɕ�ݍ���ʼn������}����B�������A����́u�ꐫ�v�̂Ȃ���s�ׂł���A �̋��͂����܂ł��߂�ׂ����炬�̏�ł��邱�Ƃ������Ă���B
�@���Ȃ킿�A����ɂƂ��Č̋��Ƃ́A������������Ǝ�e�̗��`���Ƃ��Ă���킯�ŁA����́A�����邪�̂ɑ����Ƃ����Z�����m�̃A���r�o�����c�Ȋ���Ɠ����ł���Ƃ����悤�B
�莝���Ԃ����ȕ��Ɩi�������̌Z�̑��݂��Ӗ�����A�����I�Ɏx�z���������Ă���Ǝ�ȕ����Ƃ́A�ʂ̌���������A���̔_���̂����ꂽ����ł�����B���̋����ŋ����ȎЉ�́A�O�ߑ�����낤���Ĉێ����Ă͂��邪�A���ɂ��̌��łȑ���͕��ꋎ�����B
�@���āA�������͂����܂����𑝂��Ă���B����͂��ꂩ����j����ʂɂƂ�Ȃ��琶���Ă������낤���A����͒��X�ƍ��Ō����L�����A�E�[�}���̒n�ʂ�s��Ōł߂Ă������낤�B����͎��オ�ߑ�̘_���ɂ��₪�����ɂ��Ƃ��đ����邱�Ƃ̏ے��Ȃ̂ł���A�f���́A���̑Δ���A�҂������ɐ�߂镃�̗l�q�▢�ܑ��̔_���̃J�b�g�Ȃǂŕ⋭���Ă���B
�@���̉f��́A���������łт̗\���������Ղ��X�Ɏ����A�M���M���̂Ƃ���Ŏc�鋌���̐��E���ꎞ�̏�i�Ƃ��ĂȂ��~�߂悤�Ƃ��Ă��邩�̂悤�Ɋ������B
�@���̖��������i���ɓc�ɂɋA�Ȃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���N��������A�R���N���[�g��ݐ����͊������邾�낤���A�_�����ܑ�����Ă��邾�낤�B��̂����X�Ƃ��ł�̓X�����܂ł���Ă����邩�B���������A�V��������������������̐��ɂ͂��܂��B
�@�c�ɂ̉Ƃɖ߂��āA��l�̌Z���������化�܂����鎞�ԁB����́A�t���I�����A�ޏ������ɂƂ��Ă�����ɂƂ��Ă��A���̊Ԃ̕����Ȏ��Ԃł͂Ȃ��������Ǝ��ɂ͎v�����B
|
 |
|
�@���m�g�j����ψ��ŁA���[���b�p���ǒ��Ȃǂ��C�����m�g�j�̊�̈�l�A���쎟�Y���̍u����Ζ��Z�ł������B
�@�`���A���̂��Ƃ�m���Ă��鐶�k����͂��Ȃ��Ǝv���܂��Ƃ����B�悭�e���r�ɏo������Ă����̂͏\�ܔN�قǑO�������ŁA�m���ɁA�قƂ�ǂ̐��k�͒m��Ȃ��悤�������B���T�̂悤�Ƀu���E���ǂł����q�������̂ɁA�����̂��̂͑������̂ł���B
�@�b�́A����S���Ȃ����������[�Y�̐l���̊T������n�܂����B���̏�ŁA�t�H�[�h�哝�̍ݔC�ŏI���̎d�����ޏ��̉��͂ł������̂́A�K���ƓV�c�K�ĂƂ������̍c���Ƃ̐ڐG�ɂ���āA�哝�̎��g�A���{�̈�ۂ����߂����Ƃɂ��̗��R������̂ł͂Ȃ����Ƃ������f�������Ă������A�Ȃ��Ȃ������[�����͂������B
���E�̂ǂ��ǂ��ɂ������ɂ́A�Ƃ����b�����������̂ŁA��w�͂����Đ��E�e�n�ɕ��C�������ۓI����������Ă���l�Ƃ����_����Ɉӎ����������A�u���v�����ߒǂ�������d���̗��ɁA��������u�ߋ��v��c������͂�����̂������A�������A�̉���̎d��������Ă����l�炵���Ǝv�����B�ߋ����A�����Ȃǂ�ǂ݉����čč\�z���Ă����͂́A�������A������������������킹�Ă��邪�A��������݂Ɍ��т��ēI�m�ɔc�����A������\������Ƃ����͂ɂ͌����Ă���B
�@�����̖k���N�j�����ɂ��Ă��A�����ƍ���̓W�J�ɂ��ăR�����g����Ƃ���ȂǁA���ɂ͂����ς茩���Ă��Ȃ������ł���B����������A�펞���̕č��}���n�b�^���v�悪�ǂ��́A�L���E����̌������ǂ��̂Ƃ������Ƃ͘A�z���邪�A����ǂ܂�ł���B�ǂ���玄�́A�ߋ������z����l�̂悤���B�������A���̐l�Ƃ̔\�͂̑傫�ȍ��ł���Ǝv�����B
�@�m�I�ŃC���e���Ƃ�������ۂ���̂́A��w���B�҂����炾���ł͂Ȃ���ƁA���̓��A���k�ɃR�����g�������A���̌����Ă���Ӗ��͓`��������낤���H
|
 |
�@���������Ȃ̂ŁA�莝���̃{�[���y���ŁA������Ǝ̂Ă�̂ɂ͐ɂ������̂ɂ������c���Ȃ����T�����B�i�����̂���X�����A�������������c�̌^�Ԃ��������ēK���̔ԍ��͒u���ĂȂ������B��̃��[�J�[�����Ŗc��Ȏ�ނ�����B���̃��[�J�[�ł��A������A�����K�i�ő���ꂽ���̂�����A���p�ł�����̂��������������A���̏�ɁA����ȁu�����[�J�[���p�Ή��\�v���u���Ă���͂����Ȃ��A�ڂ̑O�̑�ʂ̊����c�̂ǂꂩ�͎g����낤�Ɣ����Ă��Ă��A���ɍs�������Ȃ������B
�@���ǁA���̓��{�ł́A���܂������c�ɏ��肦�����̂����������c��A�����łȂ��{�f�B�͎̂Ă���Ƃ����̂��^���̂悤���B
�@�u�C���N�̂Ȃ��Ȃ����c�͐�Ύ̂ĂȂ��ł��������B�{�f�B���Ǝ����Ă��Ă����ƁA�Ȃ�Ƃ��Ȃ�ꍇ������܂��B�v�Ƃ͓X������̕فB
�@���́A���́u�}�C�����c�u�[���v�i�H�j�̉e���ŁA���̎��A�J�[�g���b�W���}�[�J�[���������B���̃p�X�e�����̃C���N����������V�X�e���B�����g���̂Ă̂��̂��肾�����̂ŁA�n���ɗD�����o�ϓI���Ǝv�����̂����A�g���Ă݂�ƑS�R�_�����Ƃ������Ƃ����������B���N�M�Ɠ����e�ʂ̃J�[�g���b�W�Ȃ̂ŁA�����Ƃ����ԂɃJ���ɂȂ�B�ǂ�ǂ������Ăǂ�ǂ�J�����̂Ă�B�t�ɍ������ăS�~���o�āA�G�R�m�~�[�Ȋ�����Ă��邾���ɁA�����A���܂������ɂ��ꂽ�Ȃ��B�Ƃ������S���B�嗬�ɂȂ��Ă��Ȃ��킯�ł���B
�Ƃ������ƂŁA���̊����c�Ƃ����A�{���A����߂ėL���Ȋ��I�V�X�e���B�g�[�^���I�Ɍ��āA�S�R�A�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��������B��́A���А��i�킹�邽�߂ɂ킴�킴�R�[�h�̍������������ɂ�������Ɠ����悤�ȁu����̘_���v�������ł����s���Ă���̂��낤�Ƃ����̂����_�ł���B
�@���āA�����܂œǂ܂ꂽ���̒��ɂ́A���A�ׂ����b���Ă���̂��A�������������͎g���̂Ăł����ł͂Ȃ����Ǝv��ꂽ����������������Ȃ��B�����A�������̏����A���̒���e�X�g�̍̓_�ŁA�ԃ{�[���y�����قƂ�ǂȂ��Ȃ邭�炢�g���B�܂�A�厖�Ȕт̎�ł���B��Ԉ����אg�̓����v���X�`�b�N�̂��̂ł��N�ɉ�����������Ɋ����c��Ⴂ�ɍs���B
�@����ŁA�}�Ƀ{�[���y���̘b���������R���������̂ł͂Ȃ��ł����B���A�̓_�̐^���Œ��ł��B
�@���A�������A�����̂悤�ȏj���ɉƂł������ƍ̓_���Ă��Ă��A�ǂ�������蓖�͂���܂���B
|
 |
|
�o��ŋ}�Ƀ������Ƃ�K�v�ɂ��܂��āA�}篁A�{�[���y�����w�������B�{���Ȃ��Ԉ����̂ŏ[���Ȃ̂����A�������������̂�����ƁA������ƍ������̂ɂ����B�Ƃ����Ă���S�~�́B
�@�{�[���y���ɂ����o�����Ƃ́A�܂��Ȃ������B���A�̑��O�b�Y�Ƃ��Ă�������肷����̂ōς܂��Ă����B
�Ƃ��낪�A���̃y���A�v�����ȏ�ɏ����₷���B�O���b�v�������Ċ���~�߂����Ă���̂Ŏ肪�ɂ��Ȃ�Ȃ��B�y����̊�����悭�A�l�ԍH�w�I�ɂ悭�l�����Ă���B����Ȏ��̕S�~�̍��͑傫���B�ȗ��A������ƕM�L�p��ɋ����������悤�ɂȂ����B
���̘b�����Ȃɂ���ƁA���̐i���ȂǂƂ����ɏ��m�ŁA�Ȃ�ł��}�C�u�[�������͕��[��������B���������A�Љ�{��}���ق����Ă��Ă������Ɠǂ�ł����B
�@�m���ɁA�Â�蕗���l�m�͕��[�i�����ցj�̓���ɌȂ̎���⊶�Ȃ������������̂��B��̉��l�ƌ����l������B
�@�悵�A����Ȃ玄���ƁA�E��ő�^����X�ɍs���āA�X�����������菄�����B�����������p�i�A���N�M�Ȃǂ��낢�댩������ǁA���ǁA�������Ƃɂ����͕̂R�t���̃{�[���y���B�^���L�^�����牺���Ă��邠��ł���B�������A���͂����͎g�킸�A�����E��Ŗ��������Ă��鏑�ރJ�S�Ɍ����t����B����ŁA�����Ƀy����u���Y��邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�Ƃ������@�ł���B
�@�����A�C�f�A���Ƃ��̏u�Ԃ͎v�����̂�����ǁA�u�����l�������ɖj�Ȃ���A�ᖡ�̕M�L��ł����ނ�ɕM�𑖂炷�v�Ƃ����C���[�W�Ŕ����ɍs�����̂ŁA�����̎�|����͂���āA������Ƃ������肵�Ȃ������B
�����ŁA���߂Ċ��̒��߂Ă݂�ƁA���ɂ͋��Ȃ̎��Ƃ��瑡��ꂽ�����u�����̃{�[���y�����������B�X�g�b�N�̐c�����čŋ߂͎g���Ă��Ȃ��B�悵�A������~�o���A�ǂ�ǂ�g���ă��b�`���𖡂킨���ƌ��S���āA����A�܂��A���̓X�Ɋ�����B
�@�{�[���y�����t�B���i�����c�j����܂���Əo���Ă��Ă��ꂽ�l�i���ċ������B��{��~���B���{���̌��\���������̃{�[���y���������Ă��܂��B�ł��d�����Ȃ��B�u���ꉺ�����B�v
�@������ƃJ�b�R���悤�Ǝv�������łȂɂ��ƕ�����ł���B��̂��镶���⍂���M�L�p����{��������Ɋ��ɒu����Ă��āA�u���ꂼ�j�̃X�^�C���I�v�Ǝ咣���Ă��鏑�֎ʐ^��j�����Ȃǂł悭�������邯��ǁA�����c��{�ŋ������Ă���悤�ł́A����A����ȕ��ɂȂ肻�����Ȃ��B
�@����ς�A�S�~�����{�[���y����R�t���݂����ȁA���p�{�ʁA���������H���ł������ƁA�}�ɏ��������S��ς��܂����B�w�i�w�i�w�i�B
|
 |
|
�@���L�̃J�e�S���[�Ɂu����v�Ƃ������ڂ�V�݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂��Ƃ��A�ǂ�ǂ���̂�����B���N�ɓ��艽�x���̎�̘b������Ă��邱�Ƃ��c�c�B
�@�f�W�^�����t�̃o�[�W�����A�b�v�̈ē����������̂ŁA��Ƃ�������s���g���킹�̍쓮���������Ȃ�A�}篁A�C���ɏo�����B�ꃖ�������邻���ŁA�H�̎ʐ^���a�ɁA������Ə��݂Ȃ������B
�@����A�������̃r�f�I�J�����������������Ă��߉ށB����͐V�K�w�����邱�ƂɂȂ��āA��X�T�͓d�@�X�߂��肾�����B
�@���Ȃ́A�����̂Ƃꂽ�o�b�O�́A���̃u�����h���c�V���b�v���n���S�ݓX�ɂł����Ƃ��ŁA�E��Œ����ɍs�����B
�@�ƒ�p�̏[�d���n���f�B�|���@�̏[�d�r������Ă����B�������K�v�ŁA����A�ǂ�����������A���[�J�[�̒n���c�Ə��ɓd�b����ꂽ�B���ڎ������߂����̂ł����Ɛq�˂���A������ł��t���܂����A�z�[���Z���^�[�ł�OK�ł��Ƃ̂��ƁB�萔���������̂ł��傤����d���A��ɂ�����Ɋ��܂��ƌ�������A�����A�b�͋t�ŁA������͒艿�����A������X�͊�������Ă����Ƃ̂��ƁB�]�v�Ȍo�H���������Ă�����������Ƃ����V�X�e���ɂ�����ƈ�a�����c�������A�������A�������������B��̋x���A�z�[���Z���^�[�ցB�܂��A�V�i�����̂ƕς��܂������ł����ƓB���h������B
�@����ɂ��Ă��A�[�d�r�͂ւ������́B����I�Ɍ������K�v�Ȃ��̂����[���ɓ������Ă����āA�u�C�������v�Ȃ̂́A�������Ȃ��̂��B
���ɁA�d�C�E�������l�̏Ǐ�A�\�ܔN�I��̒P�i�b�c�v���[���[�����X�L�����L������܂��A�≖�J�����̓����X�g���{�̓o�l���O�ꂽ�܂܁B�e���r�̉�ʂ͏�ɏ�ɂƃY���āA�u���E���ǂ̓v�b�c�����O��ԁB��������������A����������ł͂Ȃ��c�c�ƁA�����A�����o�����炫�肪�Ȃ��Ȃ�B���\�N�Ə��݃[���Ƃ������͉̂����Ȃ��B
�@���̍��z�ɂ́A������A�펞�A�u�C�����a����`�[�v�������Ă���B�������ɏo���ɍs���A�������Ɏ��ɍs���B
�@����A��̌����̋l�ߕ����Ƃꂽ�B
�@���A������C���ɏo���Ȃ��Ắc�c�B
�@�ł��A�o�����͑̂��ƁB�u���a����`�[�v�͂Ȃ��B
|
 |
|
�i�ό����z���̕Łi�u���̂����Ă���v�j�ɐV�K�A�b�v�������̂Ɠ������͂ł��B�Վ��ɂ����ɂ��f�ڂ��A���������č폜���܂��B�j
�|�\�l�������@
�@�@ �V���o�[���C�j���O�E�v���f���[�X�����w�Ō�̗��x���Z�����
�@�j�[���T�C������̃R���f�B�B�}�U�R���C���̐^�ʖڂȒ��N�j���A���̃A�o���`���[���Ƀ`�������W���悤�ƕ�������O�����́B���}�������߂��l�����A�������Ə���ς܂������������l�ȁi�����݂ǂ�j�Ɛ܂荇�킸���܂������Ȃ��ꖋ�ځA���D�u��̒��˂��Ԃ薺�i�^�D�R�G�j�Ƀ}���t�@�i�܂ŋz�킳��A�|�M����ďI���ځA�T�a�ŔY�ޗF�l�̍ȁi�������I�q�j�Ƃ́A��܂����ɂȂ��Ă���ȕ��͋C���������ł��܂����O���ڂƁA���D�������ɕς����̓�l�ŋ��ł���B
�@���킢���Ȃ����Ƃ肪�����B�肢�͐��A���Ȃ����낤���Ƃ������Ă���B���e���ǂ��̂����̂Ƃ������ŋ��ł͂Ȃ��B���ꂼ��̏��D�̉��Z���y���߂悢�B
�@���̕���A���c�̌����ł͂Ȃ��A�����Ђ��|�\�l��l�I���ăv���f���[�X����A����A���O�ł��q�Ăԕ����B���������Ӗ��ŁA���������Ԗ炩��ߓc�E�Ɍ�サ���̂́A�c�ƓI�Ƀ}�C�i�X�ł���B�q�̒��ڂ́A�����Ɖ����̓�l�ɏW������B
�@����l�Ƃ��s�a�r�̃e���r�h���}�o�g�Ƃ����C���[�W���������A�������蕑�䔭���A���䉉�Z�ɂȂ��Ă��āA��K�Ō���ŊςĂ��Ă��������ɂ������Ƃ��Ȃ��A���̂�����͂������������B
�@���ɂm�g�j����e���r��̐����ԑg�ł悭��������������������́A�����炭�����I�Ȋ����̐l�Ȃ̂ɁA�T�o�T�o���F�C�H���̖��_�ɂ��Ȃ��Ă��āA���������D����Ɗ��S�����B
�@�e���A�O�\��������ƁB���������x�e���߂āu�ʂ��v�ł���āA�~�j�V�A�^�[������ŏ㉉������A�����Ȏŋ����Ǝv������������Ȃ��B���Ƃ��Ƃ���������{�ł͂Ȃ��̂��H
�i���Ɠ�l�͒m��Ȃ����x���̉����t�@���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i�Q�O�O�U�E�X�E�R�O�j
|
 |
|
 �@�O�ɏЉ��G�E�~���o�b�V�i���j�̃��C�uCD�̂��Ƃ��o�Ă��Ȃ����ƁA�u���������v��HP���ςĂ��āA�`�����[�g�ivo�j�̃��C�u�����邱�Ƃ�m�����B �@�O�ɏЉ��G�E�~���o�b�V�i���j�̃��C�uCD�̂��Ƃ��o�Ă��Ȃ����ƁA�u���������v��HP���ςĂ��āA�`�����[�g�ivo�j�̃��C�u�����邱�Ƃ�m�����B
�@���������A���C�u�n�E�X�Ő����t���Ȃ�Ă��Ƃ́A�Z�N���O�A��R�́u�{�f�B���\�E���v�Őh�����Y�i���j�O���[�v���Ĉȗ��ł���B�����A�������̓W���Y�N���u�ŁA���������̂悤�ȃt�H�[�N�����郉�C�u�n�E�X�Ƃ͂�����ƕ��͋C���Ⴄ�B
�@�n���Œ������̂͂��������낤�ƋL����k��ƁA�ǂ����A��㎵���N�A�R���m��i���j��A�E���C�f�B���K�[�i���j�̃f���I���u���[�N�В��v�Œ����Ĉȗ��炵���B�������������ɂ̓��C�u�n�E�X�ł͂Ȃ��ăW���Y�i���Ƃ����ׂ��Ƃ���B�����A�В���ʂ艈���A�ׂ��K�i���オ������K�ɂ������B�����ȓX�̃e�[�u�����ǂ��āA�\���l�������X�y�[�X������Ẳ��t��B
�@���̎��A�s�A�m�̉��������Ă���ƎR������N���[�����������炵���B�q�������Ă���A�₨�璲���t������Ă��āA�r�[���r�[���ƍ�Ƃ��n�߁A��X�͂��̈ꕔ�n�I����������B������A�J���͈ꎞ�Ԓx��B����ł��N����������킸�����Ƒ҂����B���l����ƗI���Ȃ��̂ł���B�R������A���ՕI�ł��ŁA�ǂ����A�܂������ɋ����̂Ɂc�c�B
�@�����O�\�N�O�̎v���o�B
����Ȃ�A�v���Ԃ�ɂƁA���Ȃ�A��o���Ė�̔ɉ؊X�ɏo�����B�����i��\�Z���j�̂��̎��ԑтɊ`�ؔ����ӂ�����̂͒��������A�����O���Ƃ����̂ɁA�ʂ�͊ՎU�Ƃ��Ă��āA�n���s�s���S���̒n�Ւ������܂��܂��Ɗ�����Â����������B
�@�Ȃɂ����C�u�o���s���ł���B�J���ԏ��œX�ɓ��������̂́A�N����ɑ������A������������������ǂ����悤�A�̂��Ă���邩����Ƌ��Ȃ͗v��ʐS�z�����Ă����B����ł��A�X�e�[�W���n�܂鍠�ɂ͎O�\�l�قǂ̋q���Ȃ߁A���傤�ǂ������x�ɂȂ����B
�@�Ȃ͍őO��B�܂��A�V�Q�҂ł�����A�������ł������ƒ����ȂǂƂ�������i���Ƃ͂��Ȃ��B�×~�ɒ����Ƃ����ԓx���X�B
�@�܂��A��Ίw�i���j�g���I�́u�͗t�v����X�^�[�g�B���W�I�̐����t���^�ԑg�ȂǂŁA���{���w�̎��͔h���ƒm���Ă����̂ŁA�ނ�̉��t���y���݂������B�ނ̃s�A�m�́A�����h�X�^�C���̃A�h���u�̑��A�Ȃɂ���āA�t���[���̃X�P�[���A�E�g�A�n���R�b�N���̃t�@���N���Y���Ƃ�����t�@���n�m�����I�[���}�C�e�B�Ԃ���A�K���K��������������f���炵�������B
�@�u�����W���Y�Q�O�O�T�v�̈��|�I�p�t�H�[�}���X�ōX�ɋr���𗁂сA���N�A�r�b�O�o���h�Ƃ̋����A���o�����b����W�߂�ȂǁA�Ԋۋ}�㏸���̃{�[�J���X�g�A�`�����[�g�̉̂́A��\�N�I��̃x�e�����Ԃ�����������郁���n���̗������̂����Ղ�Ńp���t���̈ꌾ�B���̍��Ȃ̓[�g����ŁA�����̎����т܂Ō�����قǑ傫�������J���ăV���E�g���锭���Ɉ��|���ꂽ�B
�Ȃ́A�u�j�J�̖��v�u�o�[�h�����h�̎q��́v�Ȃǂ̃W���Y�Ȃ������邪�A�u������f���[�N�v�u�f��̂܂܂Łv�u�\���O�t�H�[���[�v�Ȃǃ|�s�����[�Ȓ��S�ŁA���Ȃ����������Ƃ���Ȃ���łȂ��݂₷�������Ƃ̂��ƁB�ł��A�L�������f�B�ׂ�����ł͂Ȃ��A�X�e�B�[�r�[�����_�[�̗L���e�[�}���`�����[�g�����b�N�r�[�g�ʼn̂�����A��]�A�����t�H�[�r�[�g�ƂȂ��ăs�A�m�����W�J�ȂǁA�ό����݂ȃ��Y���`�F���W�������ɂ����C�u�Ȃ�ł͗Տꊴ�������������B�V���o���̕@��ɍ����Ă����̂ŁA�O�l�h���}�[���@�����ۂ̃p���X���̂ɒ��ڋ����A�p���[���A�����A���Y���̃m���ȂǁA�l�l�S���Ŕ��U����A���y�����v���~�e�B�u�Ȗ��͂ɐ������ꎞ�������B
�@���Ԃ���ŃW���Y���Ƃ����A����܂ł������Ƃ̂Ȃ��o���ɁA�������Ȃ��喞�����������A�A��̓�������A���Ȃ́u�s���Ă悩������B�{�P�h�~�ɂ́A�����������Ƃ̂Ȃ����Ƃ�����ƁA�]�̎h���ɂȂ��Ă����Ƃ����b�����́B�v�ƍ����̍s���������B
�@���������ō��̃��C�u���āA����Ȉ����������A����ł���낵���B
|
 |
���肢
�@���̓��L�ɂ͋���ɂ��ẴR�����g���o�Ă��܂��B���ɐh���̂��Ƃ������̂ł����A����́A�����܂ł��l�I�Ȋ��z�ł���A���悢����ւ̒ł�����܂��B���`���⒆���ɂȂ�Ȃ��悤�z�����Ă������ł��B�@�����A���ɂȂ肻���ȕ���������܂�����A���[���ɂĂ��m�点���������B
�@ ���z�������������B���́u���̂����v�̃t�H�[���́A�R�����g��g���b�N�o�b�N������u���O�`�����̂��Ă���܂���B���ʓ|�ł��A���̉^�c�ҏЉ�a�n�w�ɂ���A�h���X�𗘗p�������B
 �i�}�C�m�[�g�p�\�R���ƍ��͖������v�@2005.6�@���R�[�@�L���v���IGX8�j �i�}�C�m�[�g�p�\�R���ƍ��͖������v�@2005.6�@���R�[�@�L���v���IGX8�j
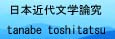
|

 ��ʁu���̂����v�ł��B
��ʁu���̂����v�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �u���Ƃ����v�Łu�Ƃ�Ƃ߂̖����b�v���ƈ��삳�����Ă���悤�ɁA�F�l���m�A�H�������ɂ��Ȃ���̎G�k�Ƃ����������ŁA��������������������A�y�������������B
�u���Ƃ����v�Łu�Ƃ�Ƃ߂̖����b�v���ƈ��삳�����Ă���悤�ɁA�F�l���m�A�H�������ɂ��Ȃ���̎G�k�Ƃ����������ŁA��������������������A�y�������������B �\�N���炢�O�ɎB���������ʐ^�ɊȒP�ȃG�b�Z�C�����B���X�F�Ă�����̂���Ȃ��ōڂ��Ă���̂̓m�X�^���W�[�̉��o�ł��낤�B���ۂ̉����Ɍ��肵�����̂ł͂Ȃ��Ƃ����Ƃ��낪�~�\�ŁA�R�̎�̎ʐ^��������B�����Ƃ����C���[�W�ō\�������u�܂ڂ낵�̒��v�Ƃ����R���Z�v�g�ł���B�������݂ȕ��i�����邵�A������Ď��݂��Ȃ����̂�����Ƃ����B
�\�N���炢�O�ɎB���������ʐ^�ɊȒP�ȃG�b�Z�C�����B���X�F�Ă�����̂���Ȃ��ōڂ��Ă���̂̓m�X�^���W�[�̉��o�ł��낤�B���ۂ̉����Ɍ��肵�����̂ł͂Ȃ��Ƃ����Ƃ��낪�~�\�ŁA�R�̎�̎ʐ^��������B�����Ƃ����C���[�W�ō\�������u�܂ڂ낵�̒��v�Ƃ����R���Z�v�g�ł���B�������݂ȕ��i�����邵�A������Ď��݂��Ȃ����̂�����Ƃ����B

 �u���ԁA�H���A�Ґ��̐��E���y���ށv�i�����U�����c�j�Ƃ������̈�Ƃ��Ď��{���ꂽ�u�O�����f���f��v�̑�����ς�B����A�ꏊ�͋���s�����}���ٓ�K�I�A�V�X�z�[���B�f��́A�����Ґ�����u���ɂ������Ɓv�i��f�j�B���a��\���N�A��������j�ē�i�ł���B�ڂƕ@�̐�ɕ����I�{�݂����邱�Ƃ̗L������������B
�u���ԁA�H���A�Ґ��̐��E���y���ށv�i�����U�����c�j�Ƃ������̈�Ƃ��Ď��{���ꂽ�u�O�����f���f��v�̑�����ς�B����A�ꏊ�͋���s�����}���ٓ�K�I�A�V�X�z�[���B�f��́A�����Ґ�����u���ɂ������Ɓv�i��f�j�B���a��\���N�A��������j�ē�i�ł���B�ڂƕ@�̐�ɕ����I�{�݂����邱�Ƃ̗L������������B �@�O�ɏЉ��G�E�~���o�b�V�i���j�̃��C�uCD�̂��Ƃ��o�Ă��Ȃ����ƁA�u���������v��HP���ςĂ��āA�`�����[�g�ivo�j�̃��C�u�����邱�Ƃ�m�����B
�@�O�ɏЉ��G�E�~���o�b�V�i���j�̃��C�uCD�̂��Ƃ��o�Ă��Ȃ����ƁA�u���������v��HP���ςĂ��āA�`�����[�g�ivo�j�̃��C�u�����邱�Ƃ�m�����B �i�}�C�m�[�g�p�\�R���ƍ��͖������v�@2005.6�@���R�[�@�L���v���IGX8�j
�i�}�C�m�[�g�p�\�R���ƍ��͖������v�@2005.6�@���R�[�@�L���v���IGX8�j