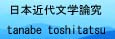|
ものぐさ 徒然なるままに日々の断想を綴る『徒然草』な らぬ「ものぐさ」です。 らぬ「ものぐさ」です。
内容は、文学・言葉・読書・ジャズ・金沢・教育・カメラ写真・弓道など。一週間に2回程度の更新ペースですが、休日に書いたものを日を散らしてアップしているので、オン・タイムではありません。以前の日記に行くには、左上の<前月>の文字をクリックして下さい。
・XP終了に伴い、この日誌の更新ができなくなりました。この日誌の部分は、別のブログに移動します。アドレスは下記です。
エキサイトブログ 「金沢日和下駄〜ものぐさ〜」
http://hiyorigeta.exblog.jp/
二十二日最終日。市文化ホールで「オールスター・スペシャル・コンサート」を聴く。これは有料の顔見せファイナル公演。
伊藤君子の生は初めて。ミルトンの「ブリッジ」などお馴染みの曲を数曲披露。次は向井滋春(tb)のグループ。七十年代半ば、若手ナンバーワンだった彼も、今や白髪交じりのオジサンに。ソロは少々肺活量が足りない感じで音が抜けていた。アキコ・グレース(p)はバリバリ弾くのだがトレモロが多く、ソロにストーリーがない。器量よしの力演だが、ジャズ的にはもうひとつ。坂井紅介のベースは逆によく歌っていて素晴らしかった。
ベン・ライリー・モンク・レガシー・セプテットは、御大はよほどの年寄りで、実態は編曲で有名なドン・シックラー(tp)が譜面を書き、舞台も仕切っていた。難しいアレンジで、ビッグバンド以外でこれだけ譜面に依存した舞台も珍しい。
その次のエリック・アレキサンダー・カルテットは、さすが若手ナンバーワン。彼のソロの流れは明瞭で無駄がない。トーンも揺れることがなく実にしっかりしている。このソロの明瞭且つ骨太さが評価されているのだとすぐに判った。
ファイナルは、出演者総出の合奏。次々奏者が入れ替わり、これは大いに楽しんだ。
本当にジャズ漬けの数日であった。今年初回のこのイベント。初回とは思えないほど大がかりで、賑わい創出に貢献したことは間違いない。しかし、思いのほか、地元でも知らない人が多く、また、観客に若者が少なかった。それは日本のジャスの現状でもあるのだろう。ちらりと見に行った、若者受けするはずの口ドラム口ベースの女性アカペラグループの観客がほとんどいなかったことから、若者のアカペラブームも去っているような印象だ。
来年以降も開催されることをジャズ好きは願うが、するならするなりに長期的な展望も必要であると感じた。
|
 |
|
シルバーウイークという名前まで出来た九月の五連休。町は県外客で大変な入り込みであった。沖縄ナンバーの車を見かけたのにも驚いたが、室蘭ナンバーの二人乗りバイクには目を疑った。
私自身は二日半のお休みだったが、「金沢ジャズストリート」というイベントが連日行われていたので、楽しく過ごすことが出来た。
この催し、市内各地の小広場で、プロ・セミプロ・アマのバンドが、有料・無料のジャズライブを行なうもの。同時並行的にあちこちで行なわれるので、プログラムを見ながら、市内をどう動くか考えながら見て回る。あたり外れも当然あるはずで、そのあたりもお楽しみである。
二十日は、仕事後、尾山神社境内特設ステージへ。明治大学と国立音大のビッグバンドを聞く。明治は元気のいいベイシーバンドといった印象。国立はリズム隊が強化されたコンテンポラリーサウンド。さすが山野のコンテスト一位で、音楽大学故当たり前なのかもしれないが、楽器あしらいが手慣れている。
二十一日は、駅地下広場で開催中の北陸カレー選手権なるイベント参加も兼ねて駅地下広場へ。カレーのブースが並び、食べ比べしてくださいという企画のもの。そのカレーを数皿食べた後、洗足学園の学生トリオ+1を聞く。クラリネットのカルテット。ここも音楽大学なので、うまいものである。
香林坊に移動、にぎわい広場で慶応大学のビッグバンドを聞く。オーソドックスなスタイルを基本にしつつ、ボサなど幅広いレパートリーを目指しているとかで、曲は聞き慣れたものばかり。老齢客が多かったのが印象的であった。
次は109前で「BEANS」なる地元バンドを聴く。フルートにパーカッションが入る爽やかサウンドが特色。ここではもう一つ「FLAT FIVE」なる富山のバンドも聴く。関西からゲストを呼んでのダブルサックス布陣で、モダン・ジャズの王道をゆくレパートリー。文句なしの力演であった。
その後、昨夜同様、尾山神社へ。「SAMURAIビバップ3」の後半と「カンザスシティ・バンド」を聴く。「カンザス〜」は、ブルースに根ざした古いジャズのスタイルに下世話な日本語歌詞を組み合わせたワン・アンド・オンリーの世界。自らを「隙間産業」と呼んだりして、途中のMCでも大いに笑わせてもらった。こんな楽しいバンドが日本のジャズシーンにいたことさえ知らなかった。(つづく)

|
 |
|
「第三の新人」の一人、庄野潤三が二十一日死去した。「プールサイド小景」「静物」は、家庭の脆さを日常の淡々とした生活を描く中で浮かび上がらせた名作であった。平野謙が作品を読み違えたと評価を変えたり、強力にプッシュしたりと彼の地位確立に大きな影響があった印象がある。
私の大学時代、庄野氏の御子息が在学しているという縁で、学内で講演会があり、謦咳に接したことがある。穏やかな話しぶりで、難しい文学論というより生活の報告のようなお話だった記憶がある。それはその頃の氏の穏やかな家庭小説そのままのようなイメージで、当時、生意気盛りだった私は、生活の陰に潜む危機感を描くのを忘れてしまっては、小説として余りに弱いのではないかという気がしていたので、講演にそれと同じ物足りなさを感じた覚えがある。
記憶をたぐると、第三の新人では、安岡章太郎、遠藤周作両氏の講演を聴いている。この際、その印象記も記したい。
安岡さんの講演を聴いたのは、同じく四半世紀ほど前、東京九段下の九段会館でだった。確か岩波書店肝煎りの講演会で、講師は学者さんとお二人。最初は軍事が専門の大学教授で、核弾頭巡航ミサイル「トマホーク」の脅威についての話、安岡さんはアメリカ滞在の時の印象記だった。
学者さんの現実的かつ分析的な話の後に、安岡さんの素朴な実感話があって、二つの毛色の違いにびっくりしたが、異種を組み合わせた方が聞き手は飽きないとも言えるわけで、いい方法なのかもしれないと後で思った。
この日のことをなぜはっきり覚えているか。それは、安岡さんとトイレで連れションしたからである。古い会館なので、講演者用トイレがないのだろう、休憩の時、我々観客が使っていたエントランス横のトイレに、ご免なさいよという感じで入ってきた。観客と講師が揃ってトイレの図は、なんだか微笑ましくて、話の内容はうろ覚えだが、それだけははっきり覚えている。
もそもそとしたしゃべり方で、行きつ戻りつ、ようやっと話をまとめたといった感じだった。ご本人も繰り返し弁解していたが、人前でのお話は苦手そうだった。
遠藤周作さんも、やはりその頃、別の講演会でお話を聴いた。小学館かどこか出版社の肝煎りで、場所は有楽町あたりのホールだったはず。いたずら好きな狐狸庵センセイであるから、もっとひょうきんな人かと思ったが、意外に低いお声で、真面目に話された。この時も、通路におられた時にチラリとコート姿のお姿を拝見したが、長身なのには驚いた。外人と並んでも遜色ない身の丈である。どことなく着こなしもダンディな印象の人だった。
実は小島信夫もどこかで聴いたはずだが、さっぱり思い出せない。
いずれにしろ、懐かしい学生時代の体験。
庄野潤三は享年八十八歳。安岡は一つ上のはずである。
|
 |
|
こまつ座「兄おとうと」を観る
民本主義の吉野作造と官僚として大臣にまでのぼりつめた弟信次の対立と兄弟愛の物語。
原作は単行本になったすぐに読んだ(新潮社・二〇〇三年十月発行)が、字面ではもっと対立しているイメージだった。しかし、芝居では、まわりの登場人物の動きや細かい動きも大きく印象に加わってくるからだろうか、底にある兄弟愛の部分がしっかり描かれていて、イメージが違った。再演の際、手直しがあったということなので、そのあたり、補強しているのかもしれない。
芝居ではピアノが伴奏で、歌が時に混ざる。そのせいで、そういえば、井上芝居を観るのは久しぶりだったということに気づいた。そのくらい彼の芝居のひとつの型になっている。
作者の主張は、国民を憲法の中心とする吉野作造の上に載っており、弟信次は対立項的存在で、判りやすい。
日本は法治国家なのだから、法(天皇主権の旧憲法)の網を守れというのは当然のことだとする弟と、「勉強したい子が中学に上がれないのはなぜ」という疑問を「がっちり受け止める法律をなに一つ用意していない」のだから、「安心して法の網に身を預けることなどできない」と批判する兄。二人はついに絶交するに至る。
作者は、吉野が、弱者や貧者を救済する施設など、本来、「日本にはすでになければならないのにまだないもの」を自力でどんどん創立してしまう「一人でやろうとする病」にかかっていると登場人物に指摘させている。それは、そのまま作者の吉野像なのであろう。
彼は、それら事業を成り立たせるために、講演会を掛け持ちし、書きまくらねばならず、常に「世間に顔を出していないと不安な、目立ちたがり屋」の「街頭学者」だと世間から馬鹿にされていると信次に指摘させている。これも、当時、誹謗的評価も決して少なくなかったことを作者は我々に知らせている訳で、国民に人気はあったものの、今の感覚で言うと、多分にジャーナリステックな側面があり、決して厳格なだけの学術的な人物として評価されていた訳ではなかったというイメージが伝わってくる。こうした点にも触れることで、堅苦しく見られがちな学者が主人公のこの物語に、人間的魅力を植え付けようとしているのである。
後半、二人の対立は理想主義と現実主義の対比でもあることを、作者ははっきりと示しはじめる。「五十すぎての理論は、すべて幼稚な空論にすぎない」と信次は言う。作造は、心底、理想主義者であった。それも底抜けにお人好しの楽天家。理想を求めて何が悪いんだという態度を本人は貫く。この生き方を見るにつけ、我々観客は、近年、理想を忘れ、弟信次のように現実主義でしかものを見ていなかったことに気づかされる。
最後の再会の場では、姉妹である二人の妻たちが、示し合わせて夫たちをだまし、旅館で引き合わせる。妻たちは、旦那の寝言から、本当は嫌っている訳ではなく、実は各々をすごく心配していることを知っている。あれだけボロクソに言う弟でさえ、東大教授から朝日新聞顧問へ、それも半年で辞職という、世間的に観ると下降選択をし続ける兄を「もったいない」と心から心配しているのである。
その作戦は、図に当たり、二人は仲直りをする。「法の網をもっと緻密に張り巡らせる」ことで国民に真っ当な生活ができるようにするという信次に、それならそれで「しっかり性根を据えてかかれ」と励ますことで、命が長くはない兄は、弟に日本の未来本を託すのである。
昭和初期、議会無視の軍国主義が台頭する中で、立場は違えど、目指しているものは実は同じ。その目標が風前の灯火になっている状況の下、二人ははじめてお互いの考えを認めることができたのであった。
ただ、この物語の主題上の結論はそれでぴったりと「締め」になっているが、これまでの話の流れから、人間的な関係の修復にまでさっと至ってしまう結末は,少し性急すぎて、話を終わらせるためのような感じが残ったのは些か残念であった。
場面はエピローグに入る。作造は程なく亡くなった(昭和八年)と妻たちの唄によって我々にしらせ、その他の登場人物のその後を語る。そして「これでおしまい兄おとうとのはなし」と子供芝居的な御陽気な歌詞で終わるのである。
作者の主張はおそらくこうである。右翼の青年を出してきて、右翼の立場を喋らせ、天津で教えた袁世凱の娘を出してきて、金と力の独裁ではダメなことを語らせる(実際は袁世凱の長子の家庭教師)。では、国の根本は一体なんだという問いを出してきて、それは民族でも言語でも歴史の共通性でもないと一つ一つ外していき、最後に、「ここでともに生活しようという意志」「ここでともによりよい生活をめざそうという願い」だと語らせる。それが、作者なりの吉野の民本主義理解の核心である。いわば、民族を超えたグローバリズム的な、アメリカの建国精神とも共通する人間愛的な博愛精神である。これは、あるいは、吉野の思想を利用した井上自身の願いそのものであるといったほうがよいかもしれない。おそらく井上は、自分の作品の主題が理想主義的で空虚だと批判されることは重々判っているのだ。その上で、でも、それを忘れてはいけないのではないかねと開き直って問いかけているのだろう。それをどう受け取るかは今度は我々の判断だ。
人物伝として、井上はこれまで樋口一葉など何人もの伝記的作品を書いてきたが、これもその一つ。手法的にも同じやり方を踏襲している。一人だと弱いと踏んで、弟と対比することで、小難しくなりがちな政治論も判りやすく封じ込めることが出来ている。その手腕はさすが手慣れている。
吉野家には十二人の子がおり、作造は長男、信次は三男であった。本当は、大勢の中で一番仲のよかった兄弟だったという。信次の役人生活の中で、色々と便宜を図ってやったり、助言などもしていたという。同じ国が相手の仕事に進んだのだから、いわば同業者的親近感も他の兄弟より強かったのだろう。
他の登場人物では、出入りしていた青木存義なる人物も実在している。芝居の通り、唱歌の仕事をしており、童謡「どんぐりころころ」の作者として名が残っている。そのあたりの綯い交ぜのしかたは天才的である。
ただ、兄の死後、大臣にまで出世した弟に対し、妻玉乃の歌の歌詞で「兄の教えがこの弟に生かされたのか、よくわからぬ」と言わせている。しかし、これは、おそらく作者の正直な感想には違いないだろうが、ちょっと「逃げ」をうった気がしないでもなかった。ここまで来て、「わからぬ」で放置のままはちょっとないだろう。
他に、四幕目、同宿の町工場主人と人買い女が実は兄妹だったという話は、議論ばかりになってしまうのを避けるために出してきた「具体例」を企図したと思われるが、うまく絡んで効いているという感じは受けなかった。再会できて「めでたし」という話にせず、行き違いで終わるなど、もっと民の苦しさを直接訴える挿話のほうが、逆にシンプルに観客の心に刺さって効果的だったかもしれない。もっと、この辺りの展開が面白ければこの作品の評価もあがったはず。名作というにはちょっと弱いところ。
役者は六人のみ。しかし、それを感じさせない。本の上手さと共に役者の技量も褒めねばならない。歌は皆巧み。剣幸という女優さんは宝塚出身という。道理で。辻萬長さんは井上芝居の大看板。存在感たっぷりである。
吉野作造記念館のWEBサイトによると、晩年、信次は次のように書いたそうだ。
「兄の民本主義思想は危険視され、世間からは相当迫害、少なくとも白眼視されたまま、昭和8年、55才で世を去った。当時愚兄賢弟の噂すらあった。世の中が落ちついてみると、やはり私たち兄弟は賢兄愚弟と相場がきまったらしい。」
民本主義とは民主主義のこと。兄の先見性は明らかで、弟の世俗的成功など世の代が変わると、もはや知る人とて少ない。信次の口吻は、兄への思いにあふれている。(2009・9・19)
|
 |
亡父が役員をしていた障害者団体から感謝状を戴けるということで、愚息が年度総会に出席して受け取ってきた。
亡父とゆかりの深い方で私も見知っている方にはご挨拶できたが、お顔は見たことがあるがどなただったかという方には、どう挨拶したらよいか判らず、そのままになって、後で、ああ、あの方だったかと思った方がちらほら。どうしようもない。
会では最初に物故者黙祷があり、途中、壇上の来賓挨拶の中で亡父に触れられた方がありと、残された家族として有り難いことであった。
そろそろ一周忌となり、それを過ぎれば、こうした行事も一段落となる。亡父の業界の方とも自然に疎遠となるだろう。本人がこの世にいない以上、それは自然なことである。
会を参観していると、普通なら本人がすっとやってしまうことも、すべてヘルプが入りながらの進行で、障害者が公ごとをスムーズに動かすだけでも大変なことであると改めて感じた。そういえば、小さい頃から父の手引きなどをよくしていたが、一年近くたち、そうしたことを忘れていた自分を感じた。
午後にはアトラクションや懇親会が予定されている。決議の承認など堅い議事もついているが、会員交流の大事な場でもある。父が尽力していたこの団体が、景気後退で弱者切り捨ての風潮の中、今後も末永く、皆、負担感なく和気藹々と過ごすことができる集まりであり続けることを祈り、午前の部で途中退座した。
会場は県南部。帰り、せっかくここまできたのだからと、新装なった山代温泉総湯に寄った。できて数ヶ月、桶の檜の香りが漂い、さっと汗を流す程度だったが気持ちがリフレッシュした。本当に最近、目先に追われていて、こうしたついででもないとゆっくり大浴場に入るチャンスがない。
ただ、長距離なのでドライブ気分も楽しめるかと思っていたが、エコ運転を心がけたため、これは全然だった。思ったほど平均燃費計の数値も上がってくれず、ちょっと、がっかり。
|
 |
|
内田樹「下流志向」(講談社)
教育が経済の等価交換原理に征服されていて、「なぜ勉強しなけらばならないのか?」という子供たちの疑問の横行は、知の下流志向しか生まないという論旨。我々現場人が漠然と感じている最近の子供たちの変化を明快に分析して、まったくもってその通りという気持ちで読んだ。確か同趣旨のテスト問題を読んだことがあるぞと去年の綴りを調べたら、この本そのものからの出題で、「なあんだ。」気分だった。
池田晶子「暮らしの哲学」(毎日新聞社)
一昨年、四十歳代後半で急逝した女流文筆家による哲学エッセイ。最晩年の作にあたる。内省的な、自己や人間そのものをやさしく分析するエッセイ的な文章に、時折、哲学や宗教の初歩的な専門知識が混じり、読者に思惟を誘う。決して社会的とはいえない、独り言のような部分のある文章だが、社会分析ものばかりを義務のように読まされている我々にとっては、こういう種類の文章に出会うとほっとする気持ちにもなる。現代は、あまりに現象分析的な文章ばかりになっていることに改めて気づく。
彼女の老いや病気、ペットへのつぶやきは、ほぼ同世代なので、よく判り、シンパシーを感じた。同じ時代を過ごし、同じく人生行路の半ばを過ぎた中年の感慨として……。中で、子供時代の夏休みの輝きを語った一編が出色。
癌の末の死去ということのようだが、闘病真っ最中に書かれたであろうこの文章に、そのことに触れた記述はない。彼女的な発想では、ジタバタ騒ぎたくなかったのであろうし、騒がないことで自分の立場を全うしたかったのだろう。実に、今時言葉で言えば「男前」な人であった。
元村有希子「理系思考」(毎日新聞社)
毎日新聞科学環境部記者に配属された文系人間の女性が書いた科学コラムを集めたもの。専門外故にばかされず本質的質問をして、専門家に「いい質問ですね」とほめられたとある通り、素人の立場だからこそ書けることがあるというスタンスは、わかりやすい文章に見事に現れていている。科学はおもしろいという啓蒙的立場に満ちている上、新聞のコラム記事として短い字数でうまくまとまっており、なかなかの書き手である。
|
 |
お願い
この日記には教育についてのコメントが出てきます。時に辛口のことも多いのですが、これは、あくまでも個人的な感想であり、よりよい教育への提言でもあります。守秘義務や中傷にならないよう配慮しているつもりです。 もし、問題になりそうな部分がありましたら、メールにてお知らせください。
感想をお寄せください。この「ものぐさ」のフォームは、コメントやトラックバックがあるブログ形式を採っておりません。ご面倒でも、左の運営者紹介BOXにあるアドレスを利用下さい。
 (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8) (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)
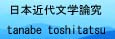
|

 らぬ「ものぐさ」です。
らぬ「ものぐさ」です。
 (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)
(マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)