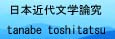|
ものぐさ 徒然なるままに日々の断想を綴る『徒然草』な らぬ「ものぐさ」です。 らぬ「ものぐさ」です。
内容は、文学・言葉・読書・ジャズ・金沢・教育・カメラ写真・弓道など。一週間に2回程度の更新ペースですが、休日に書いたものを日を散らしてアップしているので、オン・タイムではありません。以前の日記に行くには、左上の<前月>の文字をクリックして下さい。
・XP終了に伴い、この日誌の更新ができなくなりました。この日誌の部分は、別のブログに移動します。アドレスは下記です。
エキサイトブログ 「金沢日和下駄〜ものぐさ〜」
http://hiyorigeta.exblog.jp/
|
 2005年09月23日 :: 障子紙の貼り替えに悪戦苦闘。 2005年09月23日 :: 障子紙の貼り替えに悪戦苦闘。 |
|
|
|
障子は大切なもの。日本人の大発明だと信じている。
勝手に考えている理由は、以下の通りである。
1、日差しは遮るが、シャットアウトはしない。ほどよい光を入れる。調度が日焼けしない。日本の陰影文化の心臓部である。詳しくは谷崎潤一郎の『陰影礼讃』参照のこと。
2、窓を開けて寝ると夜風が入る。窓を開け障子だけを締めて寝る。適度な冷気が入り心地よい。温度や空気の調節機能がある。
3、乾いたり湿気ったりして、部屋の湿度を調節してくれる。紙の特性。
4、適度に音を遮ってくれる。空間は締め切っているのだが、淡い外との交感ができる。
昔、マンションではなく、一戸建てでの住み替えを検討した時、ある住宅メーカーの商品シリーズに、和室に障子がつかない仕様のがあった。リーズナブルな価格で魅力的だったのだけれど、候補から外した覚えがある。サッシにカーテンの畳部屋は、和室として不完全である。
障子あっての和室。
西日が入る窓の障子が変色して破れてきたので、先の休みに貼り替えた。畳の出っ張りが邪魔をして障子が外れない。いかにも今時の建物にありがちないい加減さである。前回は、結局、家具を退かして、畳をまくって、ようやく外した。今回はもうこりごりである。そこで、立てたまま障子紙をベランダ側から貼るという暴挙(!)に出た。年末には寒くて不可能な仕事。
ちょうどの大きさに切るだけでも大騒動、せっかく貼っても、風でぺらぺらめくれ上がる。曲げ皺はつく、糊が紙に付着し、黄色いシミになる。なんともはや、夫婦二人で悪戦苦闘。
でも、最後に霧吹きをたっぷりかけてそのままにしておくと、ピンと張ってさまになる。化繊百パーセントの紙ではこうはならないらしい。
和紙は偉大である。
ところで、紙などが破れることを、祖母は「やれた」と言っていた。私もそれが今の日本語だと何の疑問もなく思っていたのだが、長ずるに及び、全然、世間で通じないことを発見した。金沢の人でも通じない。あれは何だったのだろうと、この言葉を隠匿していたのだが、『土佐日記』の末尾に「疾く破(や)りてむ。」(現代語訳(この日記を)はやく破ってしまおう。)と出てきたのを読んだ瞬間、疑問は氷解した。
つまり、由緒正しい古語だったのである。祖母は、明治初期の山口県の山村生まれ、江戸の教育を受けた親から言葉を聞き覚えた。田舎には、例の言語の波紋状伝播(言葉は都を中心に波紋のように広がる。このため、田舎に古い言葉が残り、また、遠く離れた地域で同じ言葉が話されていたりすること)で、多くの古語が生き残っていたであろう。それを、婆ちゃん子の私が隔世で受け継いだのである。みんな知らない筈である。言うなれば、私の方が特殊事情。
時々、この言葉の今の認識率を、年代別に全国調査すると面白いのになあと思う。
結果、今でも思わず使いたくなるの、私一人だけだったりして……。
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
お願い
この日記には教育についてのコメントが出てきます。時に辛口のことも多いのですが、これは、あくまでも個人的な感想であり、よりよい教育への提言でもあります。守秘義務や中傷にならないよう配慮しているつもりです。 もし、問題になりそうな部分がありましたら、メールにてお知らせください。
感想をお寄せください。この「ものぐさ」のフォームは、コメントやトラックバックがあるブログ形式を採っておりません。ご面倒でも、左の運営者紹介BOXにあるアドレスを利用下さい。
 (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8) (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)
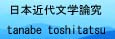
|

 らぬ「ものぐさ」です。
らぬ「ものぐさ」です。 (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)
(マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)