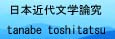|
ものぐさ 徒然なるままに日々の断想を綴る『徒然草』な らぬ「ものぐさ」です。 らぬ「ものぐさ」です。
内容は、文学・言葉・読書・ジャズ・金沢・教育・カメラ写真・弓道など。一週間に2回程度の更新ペースですが、休日に書いたものを日を散らしてアップしているので、オン・タイムではありません。以前の日記に行くには、左上の<前月>の文字をクリックして下さい。
・XP終了に伴い、この日誌の更新ができなくなりました。この日誌の部分は、別のブログに移動します。アドレスは下記です。
エキサイトブログ 「金沢日和下駄〜ものぐさ〜」
http://hiyorigeta.exblog.jp/
|
 2005年09月21日 :: (つづき) 2005年09月21日 :: (つづき) |
|
|
旧暦は、月の満ち欠けを最も上位の概念として出来ている。月を見れば今日は何日だか判る。上記のような多少の移動はあるが、月の真ん中が満月の日、古代の人類たちは、月の欠け具合を見て、一日のズレもなく、今日は何日が当てたはずである。今日は三日月よりほんの少し厚みがあるから4日だというふうに……。そうした、人間としての直感的把握を重要視していたのである。
そのかわり、「季節」面では無理があった。暑さ寒さは太陽の運行で決まるから、新暦では、各年の同月同日を較べることに意味はあるが、旧暦では、厳密には意味がない。なぜなら、時に閏月なんていう調整をいれているくらいで、近代的時間感覚で言うと、全然、固定されていないからである。
ぱっと見でわかるという「感覚」的理解こそ、前近代の人々が大事にしていたこと。よく言われることだが、これは江戸切り絵図の思想でもある。武家地・町人町を色分けし、辻に大木があれば、本当に木が書いてある。階段だと段々の線が本当に書いてある。縮尺的には歪んでいるのかもしれないが、地図としては現代より余程使いやすい。
昔の人は、正確さということにファジーだったのではない。幕府は、天文方を置いて、暦を管理していた。暦を司るものこそ為政者であるとは有名な話である。
月を見たらすぐにわかるというシンプルな思想を守るために、月の運行、太陽や星の動きを勘案しながら天文学者が決めていく。いわば、ファジーを守るために大変な努力をしてきたのである。そして、それは、今日は仲秋、お団子供えなきゃねとするような「文化」を守ってきたことでもある。
それにしても、この旧暦、調べれば調べるほど、実にややこしいことをしていたのだということが解る。授業では、月に思いを添えて和歌を詠んだりしている場面を喋るので、無責任に、旧暦の方が風情があっていいねえなどと言っているが、もう十二単衣の時代ではない。ちょっと教養を披瀝して、「今日は旧暦の○○の日でして、この日の来歴は〜。」などと蘊蓄たれているくらいが適当なのかもしれない。
|
|
|
|
|
|
|
お願い
この日記には教育についてのコメントが出てきます。時に辛口のことも多いのですが、これは、あくまでも個人的な感想であり、よりよい教育への提言でもあります。守秘義務や中傷にならないよう配慮しているつもりです。 もし、問題になりそうな部分がありましたら、メールにてお知らせください。
感想をお寄せください。この「ものぐさ」のフォームは、コメントやトラックバックがあるブログ形式を採っておりません。ご面倒でも、左の運営者紹介BOXにあるアドレスを利用下さい。
 (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8) (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)
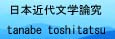
|

 らぬ「ものぐさ」です。
らぬ「ものぐさ」です。 (マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)
(マイノートパソコンと今は無き時計 2005.6 リコー キャプリオGX8)